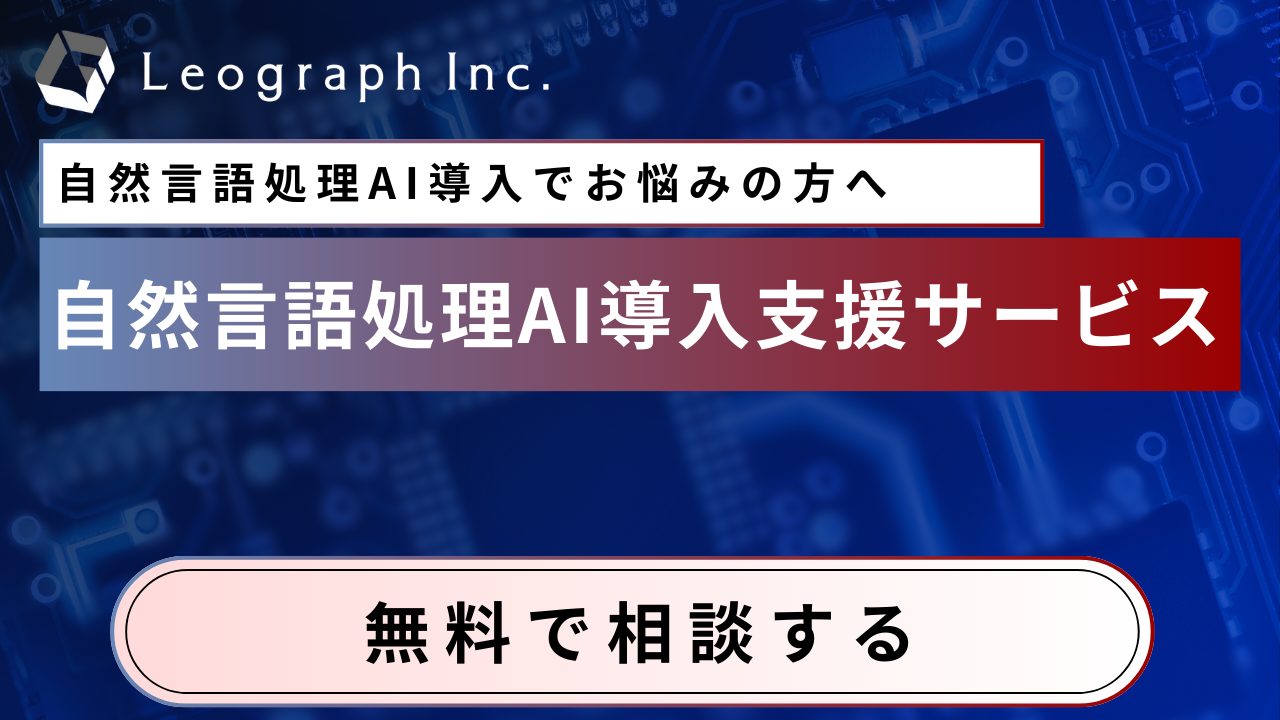日本と世界の農業AI活用事例19選!導入のメリットとデメリットとは?
農業分野でのAI活用が拡大していることはすでに自明のことですが、その背景には「先進国の宿命」があります。
というのも、日本を含む先進各国は出生率低下や生産コスト(物価, 人件費など)が高くなるなど、従来の手法では一次産業を保つことが難しくなってきているのです。
そこで解決の足掛かりとして注目されているのが「農業でのAI活用」、いわゆるスマート農業という分野です。
本記事では農業のAI活用についての概論から、海外&日本のAI活用事例をご紹介し、そのメリットデメリットとともに包括的な解説をしております。農業のAI活用への理解と導入検討の手助けとなる内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
農業でのAI活用とは?

農業でのAI活用と言っても、ひとえに「これが農業のAI活用だ!」という概念があるわけではありません。
そこには多様なニーズ・課題が存在し、AI活用もまたそれらに応えるべくして多方面での展開がなされています。
例えば気象データや土壌情報、作物の生育状況など多様なデータをAIが解析したり、栽培から収穫、出荷までの一連のプロセスを効率化・最適化するためのロボット導入などもこれに含まれます。
本節では「画像認識の農業AI活用」、「需要予測」、「自動運転」といった3つの主要技術の特徴と具体的な事例を順に解説していきます。
画像認識の農業AI活用
画像認識技術とは、AIモデルに大量の画像とラベルデータを学習させることで物体を検知したり、画像を分類したりすることができる技術です。
画像認識を用いた農業AIでは、ドローンや固定カメラで撮影した映像を解析し、作物の健康状態をリアルタイムで監視したりすることができます。
ある技術では、成熟度を検知できるAIモデルにより最適な収穫タイミングを判定し、品質の均一化と作業効率化を実現するといった事例も存在します。
また、作物が工場ラインに並ぶまでの判別(実の欠けた作物をはじくなどの作業)においても、CNN(畳み込みニューラルネットワーク)という画像に特化したディープラーニングで、半自動的に判別をするという事例も存在し、画像認識は農業におけるAI活用の代表例と言えるでしょう。
需要予測の農業AI活用
農業におけるAI需要予測とは、気象データや市場動向、消費者の嗜好など多様な情報を統合したAIが適切な種まき・収穫時期や出荷量を正確に予測したり、過剰生産や供給不足を防ぐような技術を言います。
予測精度を向上するため、AIベンダーは国が公開する気象データ・土壌データはもちろんのこと、農家と提携して一次情報を独自に解析する例もあります。
AIの需要予測は無駄な在庫を抱える必要性を抑えることから、主に農家の収益最大化に貢献し、昨今の課題であるフードロスにも解決策として注目されています。
自動運転の農業AI活用
自動運転技術とは、AI技術の中でもトップクラスに難易度の高いとされる部類とされています。画像認識やその他と違い、AIが学習すべきデータ対象があまりにも多いためです。
しかし、農業における自動運転の難易度は公道におけるそれとは違って、決まった範囲での決まった作業をこなすという点において比較的ハードルの低いAI分野といえます。
自動運転技術搭載した農業AIは、無人トラクターやドローンによる播種(種まきのこと)〜施肥〜農薬散布〜収穫などの一連の作業を半自動化することが可能です。
自動運転技術は持続可能なスマート農業の実現においては不可欠な技術と言えるでしょう。
海外の農業AI活用事例10選

海外では、米国や欧州をはじめとする先進農業国で、多彩なAIソリューションが続々と実用化されています。
大規模農場向けの自動運転トラクターや、衛星データ解析を活用した気象連携型の需要予測、画像認識による病害虫検知など、その技術領域は多岐にわたります。
IT大手も農業現場のDXには興味津々で、その技術の幅は目を見張るものがあります。
本節では、こうしたグローバルリーダー10社の具体的な取り組みと、その導入メリットを詳しく見ていきましょう。
John Deere(ディア・アンド・カンパニー)
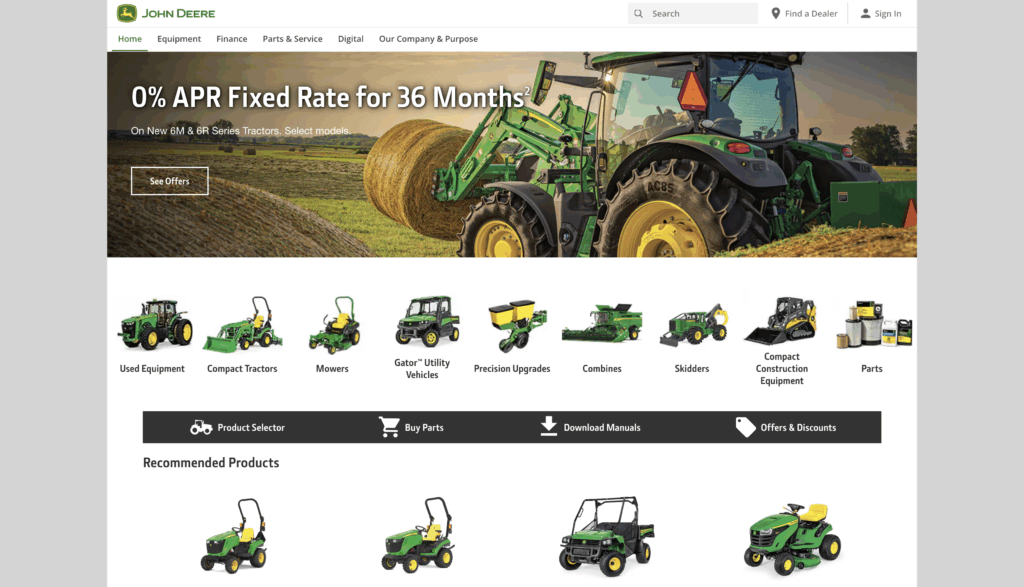
ジョン・ディア(ディア・アンド・カンパニー)は1837年に創業された米国の農機大手で、AIとビッグデータを融合させた多彩なソリューションで世界の大規模農場を支えています。
自律走行トラクターは、GPSとセンサーを活用して24時間体制の作業を可能にし、作業効率と正確性を大幅に向上し、疲労や人手不足を解消することを目指します。
さらに「See & Spray」技術は、コンピュータービジョンで雑草だけを識別し、除草剤をピンポイント散布。薬剤使用量を最大77%削減し、環境負荷とコストを同時に抑制が可能に。
最近は電動化と脱炭素を見据え、オーストリアKreisel Electric社への出資で高性能電動農機の開発を推進。
Blue River Technology
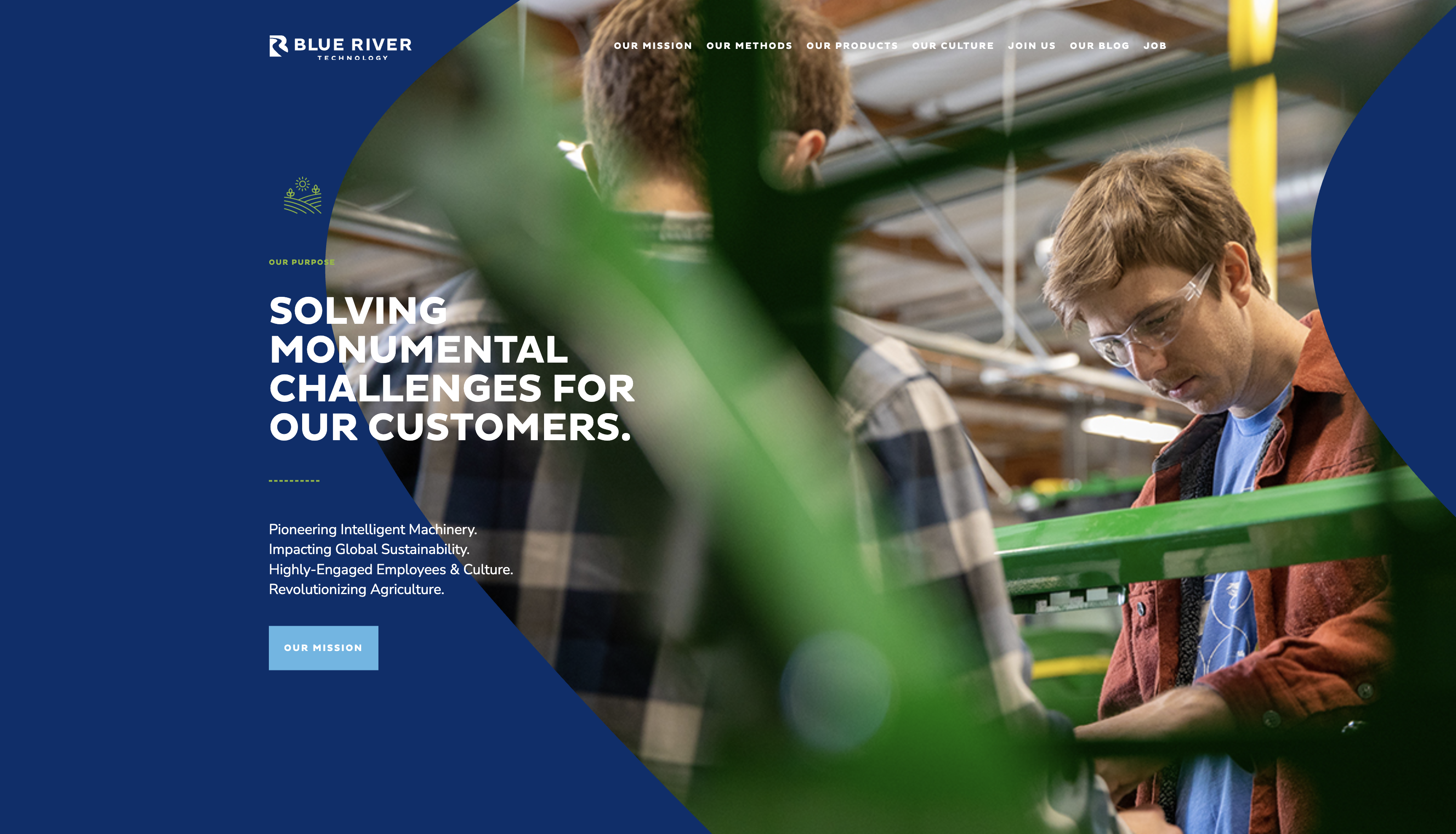
Blue River Technologyは、コンピュータービジョンを活用した「精密除草」技術で知られる米国の企業です。
カメラで畝(うね)を撮影しながら走行し、AIが作物と雑草を瞬時に識別。雑草のある箇所にだけ薬剤をピンポイントで散布する「See & Spray」などのシステムを開発し、従来の一斉散布と比べて除草剤使用量を大幅に削減します。
同社は現在、ジョン・ディアグループの一員として、トラクター搭載スプレーヤー向けにこの技術を提供しており、大規模圃場での薬剤コスト削減と環境負荷低減に貢献しています。
Climate Corporation
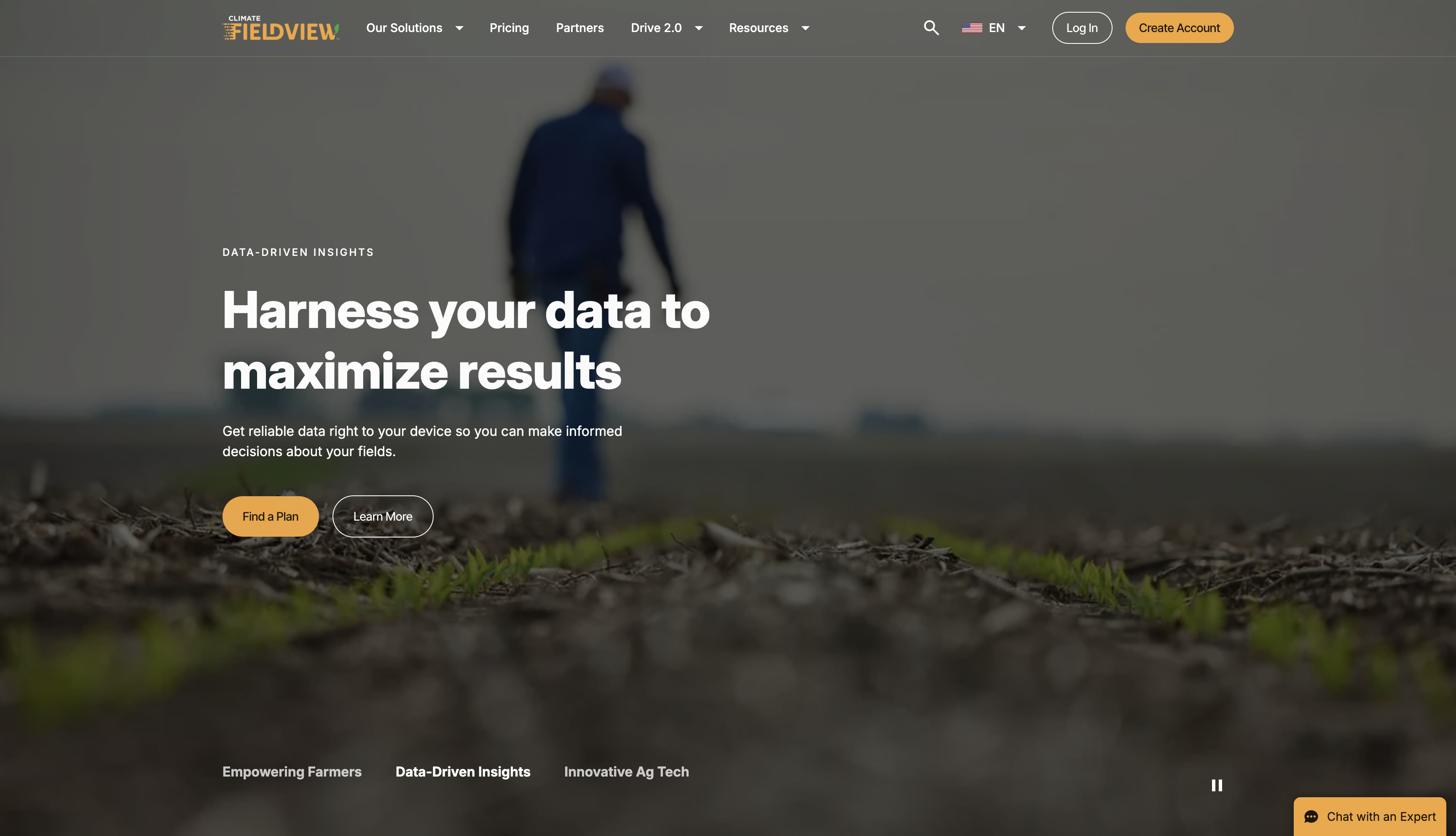
Climate Corporationは、気象データとサテライト・圃場データを組み合わせたデジタル農業プラットフォームを提供し、作物の生育状況や収量予測、肥料・水分管理の最適化を支援しています。
同社の「Climate FieldView」(前身のClimate Proを含む)は、土壌や作付け履歴、気象データなどを統合し、農家が施肥や潅水、作業タイミングをデータに基づいて判断できるようにするサービスです。
また、害虫や病害の発生リスクをモデル化し、見回りの優先エリアを絞り込むことで巡回コストを抑えつつ、被害を最小限に抑えることを目指しています。
北米を中心に利用が進んでおり、生産性向上と環境配慮を両立するデジタル農業の代表的な事例となっています。
Microsoft(Azure Data Manager for Agriculture Preview)
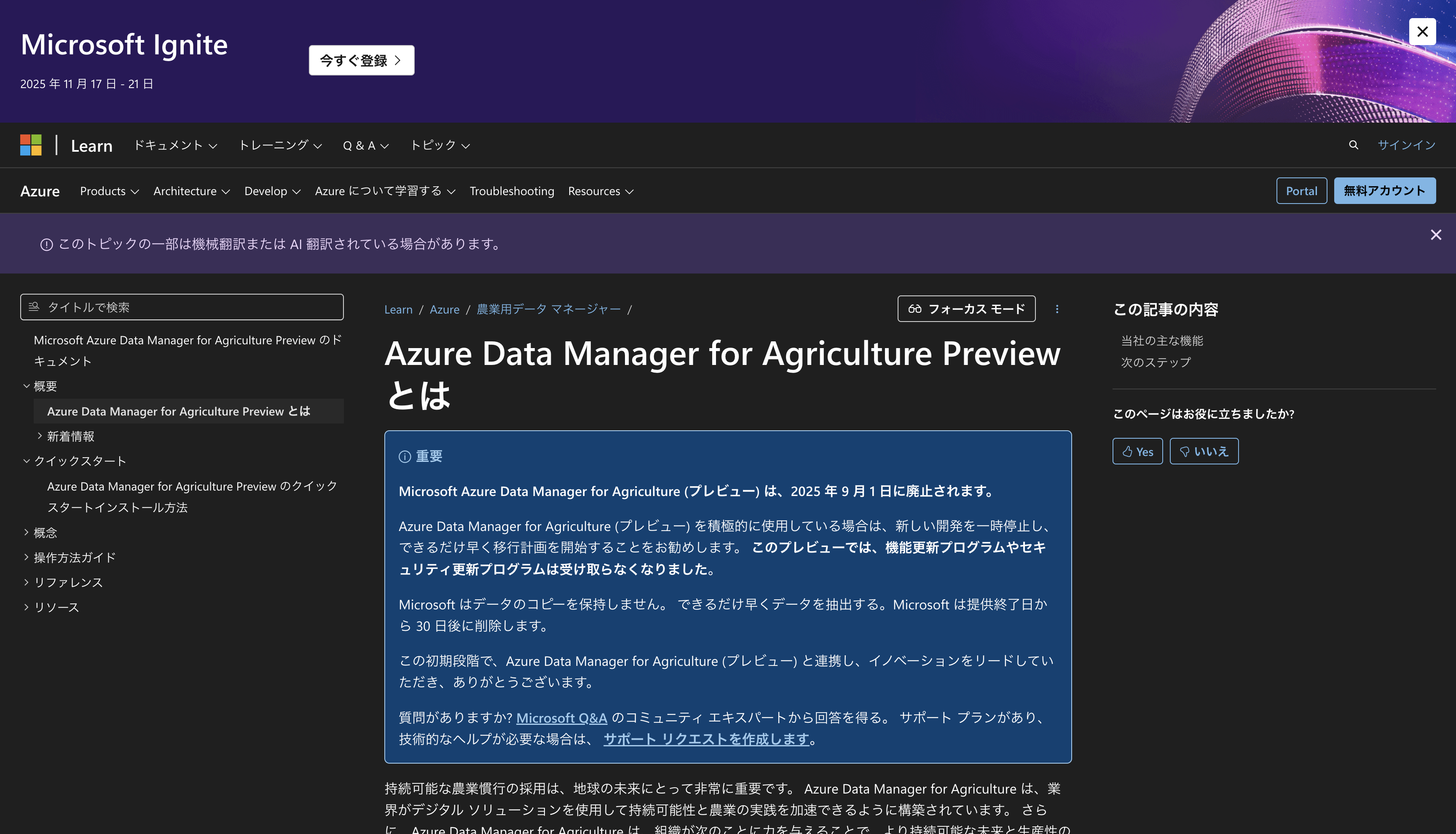
Microsoftは、Azureプラットフォームを基盤に農業分野のデジタルトランスフォーメーションを推進しています。
AIやクラウド技術を活用し、以下のようなソリューションを提供しています:
- 作物生育モニタリング
- 需要予測と在庫最適化
さらに、農業機械メーカーや研究機関と連携し、Cortana IntelligenceやCustom VisionなどのAIサービスを組み合わせた実証実験を多数実施。
これにより、持続可能な農業経営と環境保全の両立を目指しています。
参考: 農業向け Microsoft Azure Data Manager とは | Microsoft Learn
IBM
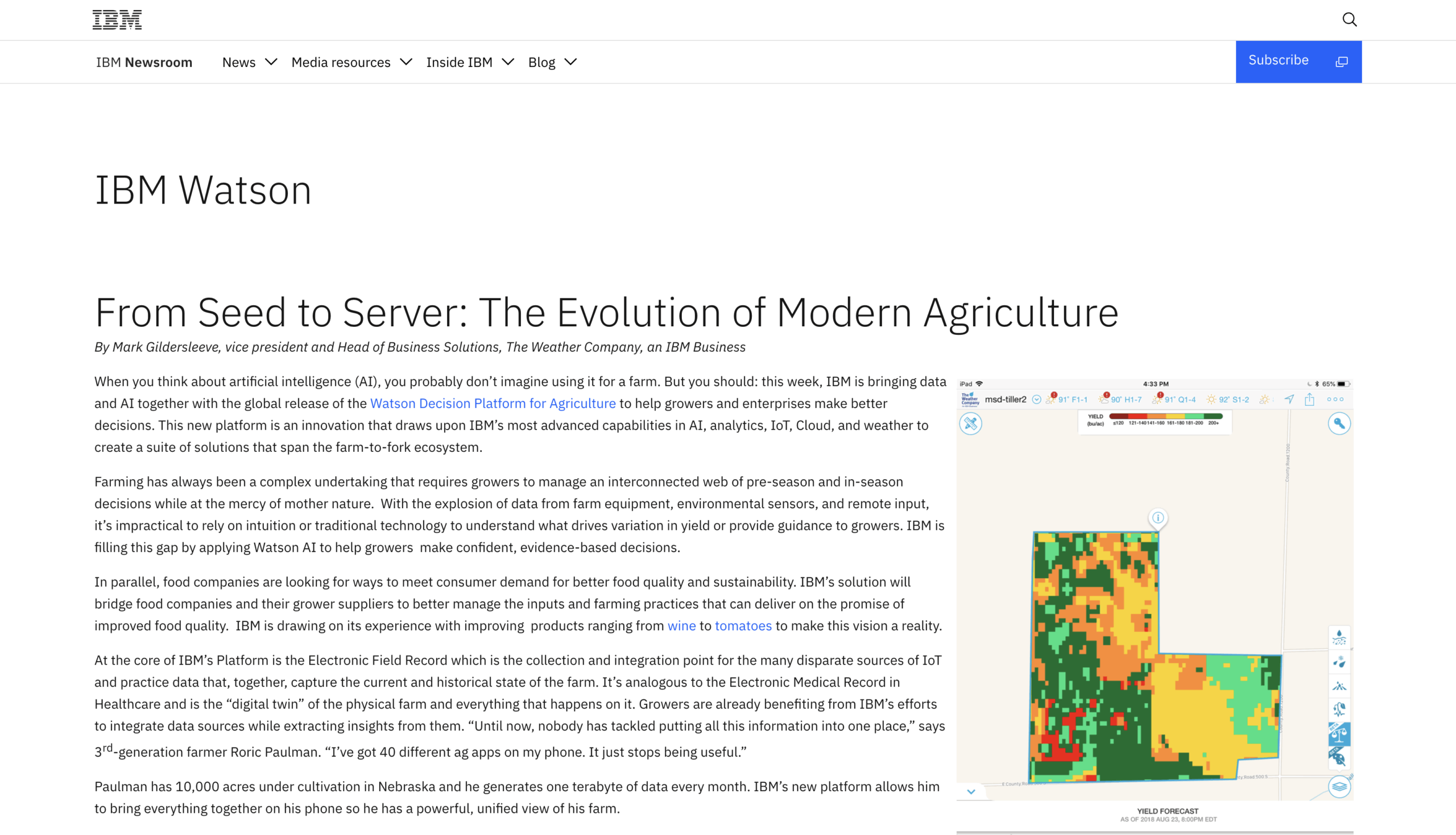
IBMは、気象・衛星データやIoTセンサー情報を統合して分析する「IBM Environmental Intelligence Suite」や「Watson Decision Platform for Agriculture」などを通じて、農業分野の需要予測や生産性向上、サプライチェーン最適化を支援しています。
これらのプラットフォームでは、天候リスクや病害発生の可能性、収量予測などを可視化し、播種・施肥・収穫のタイミングをデータドリブンに決められるようにします。
また、三井物産の「farmers 360° link」プロジェクトでは、IBMのブロックチェーン技術を活用してアフリカ・ザンビアの綿花農家から日本の消費者までの流通を可視化。
トレーサビリティの確保や公正な取引関係の構築を通じて、農家の所得向上と持続可能なサプライチェーンづくりを支援しています。
こうした取り組みにより、IBMの技術は農業現場のリスク管理とサステナビリティ向上の両面で活用されています。
参考: From Seed to Server: The Evolution of Modern Agriculture
Trimble Agriculture
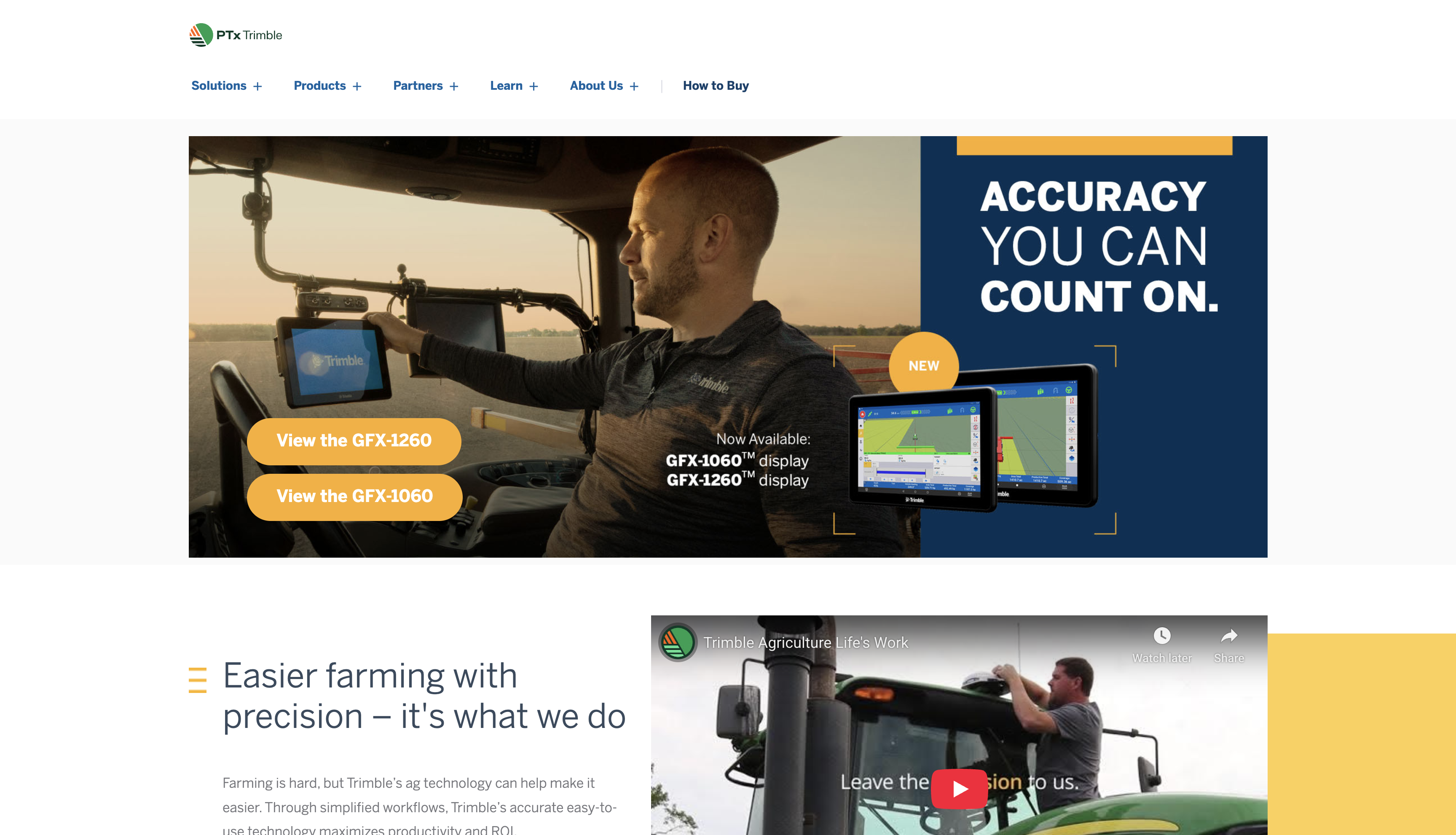
Trimble Agricultureは、精密農業技術のリーディングカンパニーとして、圃場データの可視化から自動制御まで幅広いソリューションを提供します。
主力のTrimble Ag Softwareは、作業記録や圃場マップ、気象情報、機械の稼働状況などをクラウドで一元管理し、施肥や播種の履歴を踏まえた営農判断を支援します。
光学センサー搭載のWeedSeeker 2は、雑草のある場所だけを検知して薬剤を散布するスポットスプレー技術により、除草剤の使用量を最大約90%削減できるとされています。
さらに、農機メーカー各社のデータプラットフォームと連携することで、トラクターや作業機から取得したデータと圃場情報をシームレスに統合。
Taranis
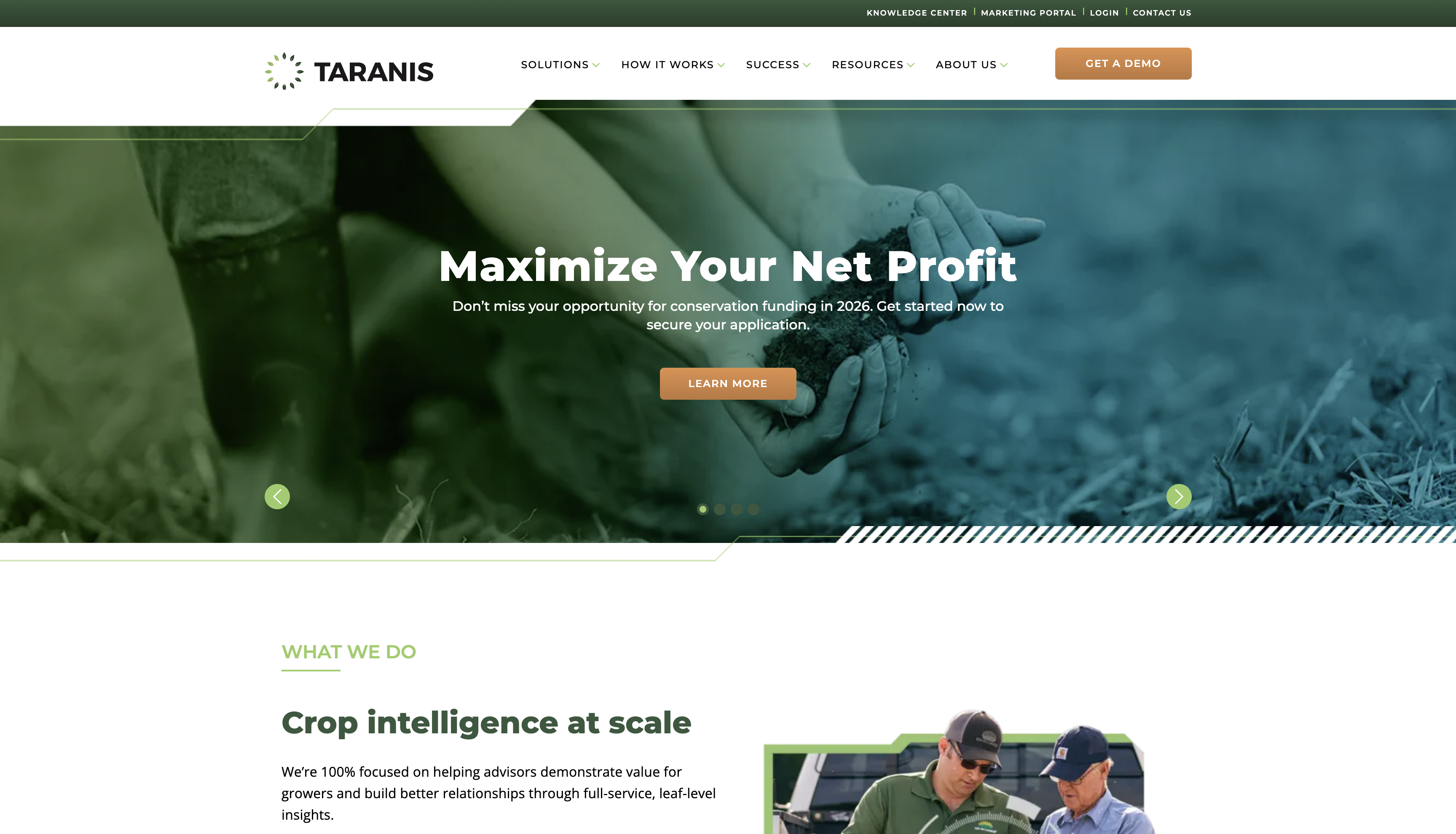
Taranisはイスラエル発のアグリテック企業で、ドローンや航空機、衛星から取得した高解像度画像をAIで解析し、病害虫や雑草、栄養不足の兆候を早期に検出する「クロップモニタリング」サービスを提供しています。
同社の機械学習アルゴリズムは膨大な画像データを自動解析し、リスクの高いエリアを地図上に可視化することで、散布や追肥の優先順位付けを可能にします。
北米やブラジル、ウクライナなど世界各地で導入が進んでおり、2022年にはシリーズDラウンドで4,000万ドルを調達。
生産者が限られた資材と時間を効果的に配分できるよう支援することで、収量向上とコスト削減の両立を目指しています。
FarmWise

FarmWise社は2016年にカリフォルニア州サンフランシスコで設立されたアグリテック企業。機械学習と画像認識を活用した自動除草ロボットを開発し、畑を自律走行しながら作物と雑草をリアルタイムに識別、雑草だけを摘み取ります。
これにより農薬使用量を大幅に削減し、作物へのダメージを最小限に抑制。 同社のロボットは葉物野菜やカリフラワー、ブロッコリーなど多様な作物に対応し、カリフォルニア州とアリゾナ州の野菜生産者に従量課金制の除草サービスを提供中。
2019年には1,450万ドルを調達し、ロボット工学や植物検出技術の研究開発を強化しています。
将来的には作物の健康状態を継続的にモニタリングし、個々のニーズに応じた処置を自動で実行する機能搭載を目指し、労働力不足の解消と環境負荷軽減を両立させる持続可能な農業の実現に貢献しています。
※2025年4月にTaylor FarmsがFarmWise事業を買収し、前述の技術は新しいオーナーシップの下で継続されています(iGrow NewsTaylor Farms)
Indigo Ag
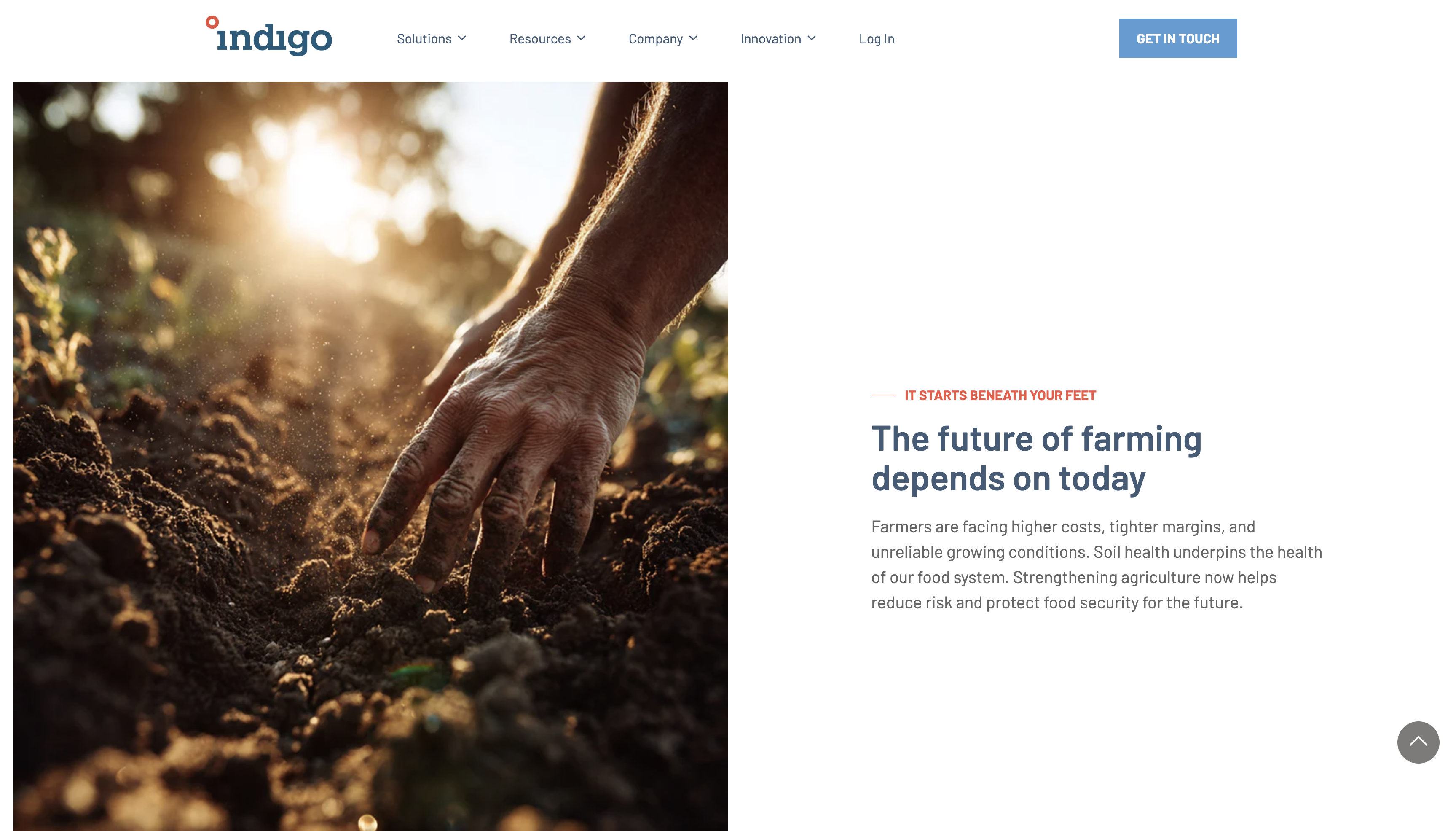
米国ボストン発のIndigo Agは、農業の持続可能性と生産性向上を同時に実現することを掲げるアグリテック企業です。
同社の農家の土壌炭素の増加や温室効果ガス削減を測定・検証し、その結果を基に 土壌炭素クレジットを発行・販売するプログラム「Carbon by Indigo」では、環境配慮型の営農をインセンティブ設計から支援しています。
微生物ソリューション「biotrinsic」では、世界中から収集した膨大な微生物ライブラリを活用し、作物や地域に応じて耐乾燥性の向上や病害ストレス軽減に貢献する種子処理資材を開発。化学肥料や農薬への依存度を下げながら収量と品質の向上を狙います。
さらに、デジタルプラットフォーム「Market+」を通じて、生産者が自らの作物の特性や栽培方法をバイヤーに直接アピールし、プレミアム価格での取引機会を得られる仕組みも提供。環境価値と経済価値の両面から農家の収益向上を後押ししています。
IUNU
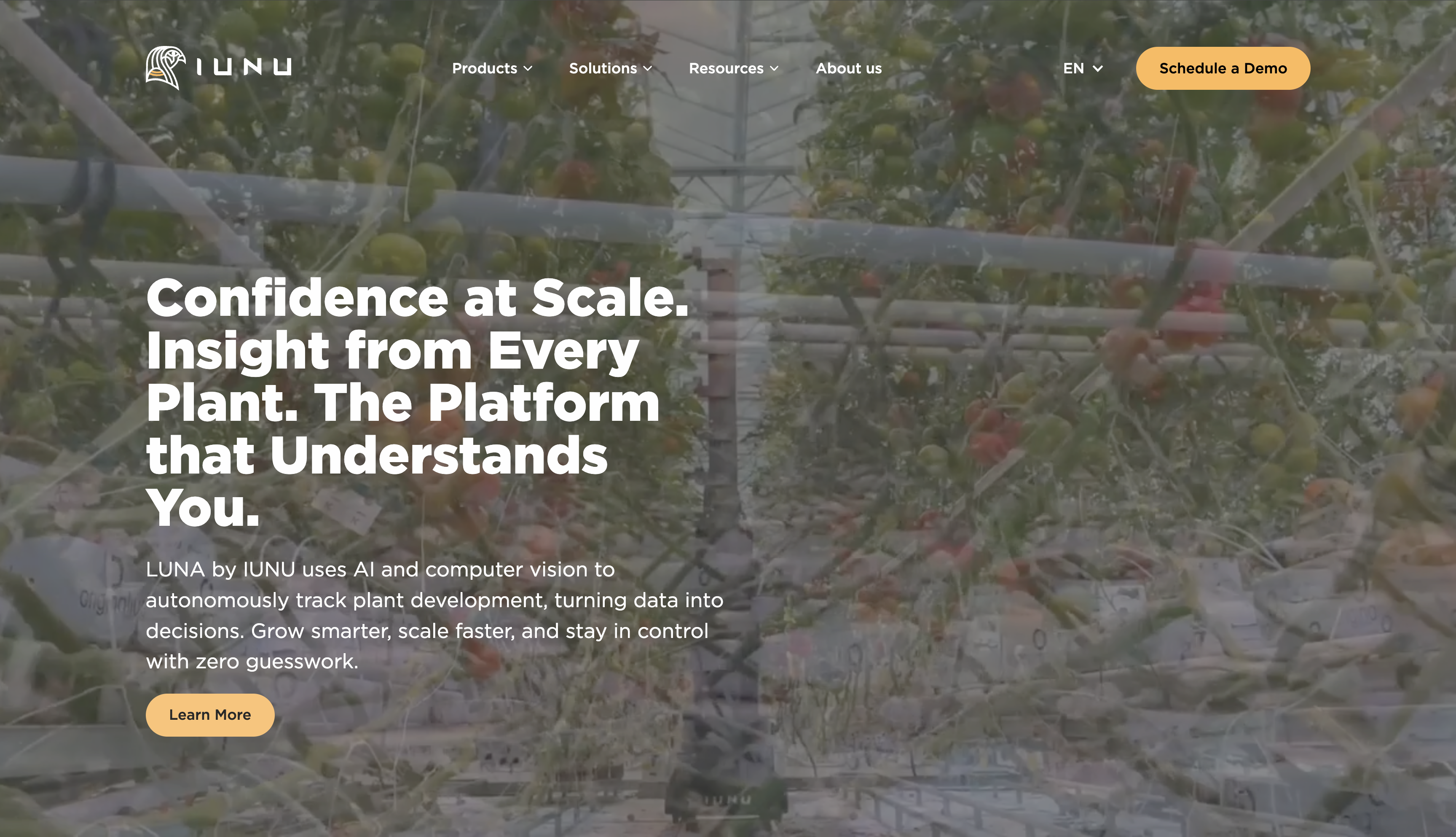
IUNUは「温室」や「制御環境農業(CEA)」に特化していますの効率化に特化した米国発のアグリテック企業です。コンピュータービジョンとAIを組み合わせた「LUNA」プラットフォームでは、温室内に設置したカメラシステムが作物の色や形状、生育密度などのデータを継続的に取得し、クラウド上で可視化します。
生育の異常や病害リスクの兆候を早期に検知できるため、農家は施肥・潅水・収穫タイミングの調整をデータに基づいて行うことが可能です。
こうした自動モニタリングによって、温室栽培の生産性向上や労働コスト削減が期待されており、より高い収益性と安定生産を目指す生産者に活用が広がっています。
日本の農業AI活用事例9選

日本の農業現場でもAI導入が本格化し始め、収量向上や労働効率化、品質管理など多岐にわたる効果をもたらしています。
特に、高齢化や人手不足に直面している国内農家にとっては、AIが作業負担を軽減し、長期的な持続可能性を支える重要な手法と言っても過言ではありません。
本節では、大手農機メーカーからベンチャー企業まで、異なるアプローチでソリューションを提供する9つの事例を紹介します。
各社の取り組みから見えてくる成功ポイントを深掘りしていきましょう。
ヤンマー

ヤンマー株式会社は、ICTやIoT、自動運転技術を農業機械に取り入れ、圃場作業の省力化と作業精度の向上に取り組んでいます。
無人走行に対応したロボットトラクター「YT5113A」は、RTK-GNSSによる高精度測位と各種センサーを用いた自動運転機能により、キャベツやタマネギなどの栽培において均一な作業品質を保ちながら、作業者の負担軽減に寄与しています。
さらに、自動操舵システムを搭載したトラクターは、島根県の有限会社コスモ21が約650枚の小規模水田で導入しており、高い直進性によって重複や空白を抑え、作業効率の向上につながっています。
加えて、IoTプラットフォーム「SMART ASSIST(スマートアシストリモート)」では、機械の位置情報や稼働時間、燃料残量、エラー情報などを遠隔で把握でき、収集したデータに基づく稼働管理や計画的なメンテナンスを通じて、運用コストの抑制とダウンタイム低減を支援しています。
オプティム

オプティム株式会社は、AI・IoT・ロボティクスを組み合わせたスマート農業ソリューションを展開している。
2020年のオンラインイベント「OPTiM INNOVATION 2020」では、播種ドローンなどを活用した農業DXの取り組みが紹介された。
同社のAgri Field ManagerやAgri House Managerでは、ドローン画像や各種センサーデータから生育状況や病害虫リスクを可視化し、収量・収穫期予測などに活用。
これらの技術により、同社は農家の省力化や営農計画の高度化、コスト削減を支援しています。
参考: AI・IoT・Roboticsを使って ”稼げる農業”を実現する | オプティム 農業×IT
クレバアグリ

クレバアグリは、ハウス内などに設置した各種IoTセンサーから得られる環境データをクラウド上に集約し、AIで解析することで、栽培状況の「見える化」と意思決定支援を行う農業クラウドサービスを提供しています。
土壌や気象、生育に関するデータを収集・整理し、ダッシュボード上で一覧できるようにすることで、経験と勘に頼りがちな栽培判断をデータで裏付けられるようにすることを目指しています。
これにより、灌水や環境制御のタイミング・量の調整、収穫量や収穫時期の予測に基づく作業計画の立案などを効率化し、生産性向上や品質の安定化を後押しします。
同社は、クラウド上にデータを蓄積して生育シナリオの最適化や経営支援に活用することで、データ活用型の農業経営への移行を支援しています。
バイエル クロップサイエンス

バイエル クロップサイエンスは、ドイツに本社を置くバイエル社の農業部門として、AIやデジタル技術を活用したデジタルファーミングを推進しています。
衛星画像やドローン画像、圃場内センサーや農機から得られるデータを組み合わせ、生育状況や病害虫・水分ストレスなどのリスクを高頻度に把握できるようにしています。
同社のサービス「xarvio」や「Climate FieldView」では、気象や衛星、圃場データを独自のアルゴリズムで解析し、圃場ごとの病害・害虫リスクや処理に適したタイミング、可変施用処方などを提示することで、農薬や肥料の過剰投入を抑えつつ収量の向上を支援。
解析結果はスマートフォンアプリやWebダッシュボードで可視化され、農家はそれを基に栽培プランや投入量を調整できるため、省力化とコスト削減、環境負荷の低減を両立した持続可能な農業経営を後押ししています。
参考: バイエル クロップサイエンス – Bayer|バイエル クロップサイエンス
システムクラフト

システムクラフト株式会社は、移動型ベースロボット「SCIBOT」や無線センサーネットワーク機器などを開発する組込みシステム企業です。
同社は、東京都農業総合研究センターとの共同研究により、ハウス内の温度管理や灌水作業を自動化する「ミストクーリングコントローラー」や、小型コンピュータを用いた低コストなハウス環境制御システムの開発にも取り組んでおり、ロボット・無線通信技術を農業分野の環境制御に応用しています。
今後、こうした移動ロボット技術や無線センサ技術とクラウド基盤を組み合わせて、ハウス内環境のデータ蓄積や遠隔監視、作業負荷の軽減につなげることが期待されており、製造・サービス分野で培った自動化技術を農業に展開していくスマート農業の取り組みの一例と位置付けられます。
参考: ミストクーリングコントローラー 株式会社システムクラフト|東京都立川市
AGRIST(アグリスト)

AGRIST株式会社は、AIとロボット技術を組み合わせて農業の効率化と持続可能性の向上を目指す、日本発のベンチャー企業です。
農林水産省・消費者庁・環境省が連携するプロジェクトの動画コンテストで受賞したピーマン自動収穫ロボットは、カメラ画像をAIで解析して収穫適期の果実を判別し、自動で収穫します。これにより、人手不足が深刻な収穫作業の省力化に貢献しています。
また、同社は農業自動化システムパッケージ「Sustagram Farm」を展開し、自動収穫ロボットと、自動潅水・環境制御機能を備えたスマート農業用ハウス、AIによるデータ解析を組み合わせて提供しています。
農業経験が少ない人でも操作しやすい設計とされており、生産データや需要予測を活用しながら、生産性と持続可能な農業経営の両立を支援しています。
参考: AI農業 | スマート農業DXのAGRIST株式会社
inaho(イナホ)
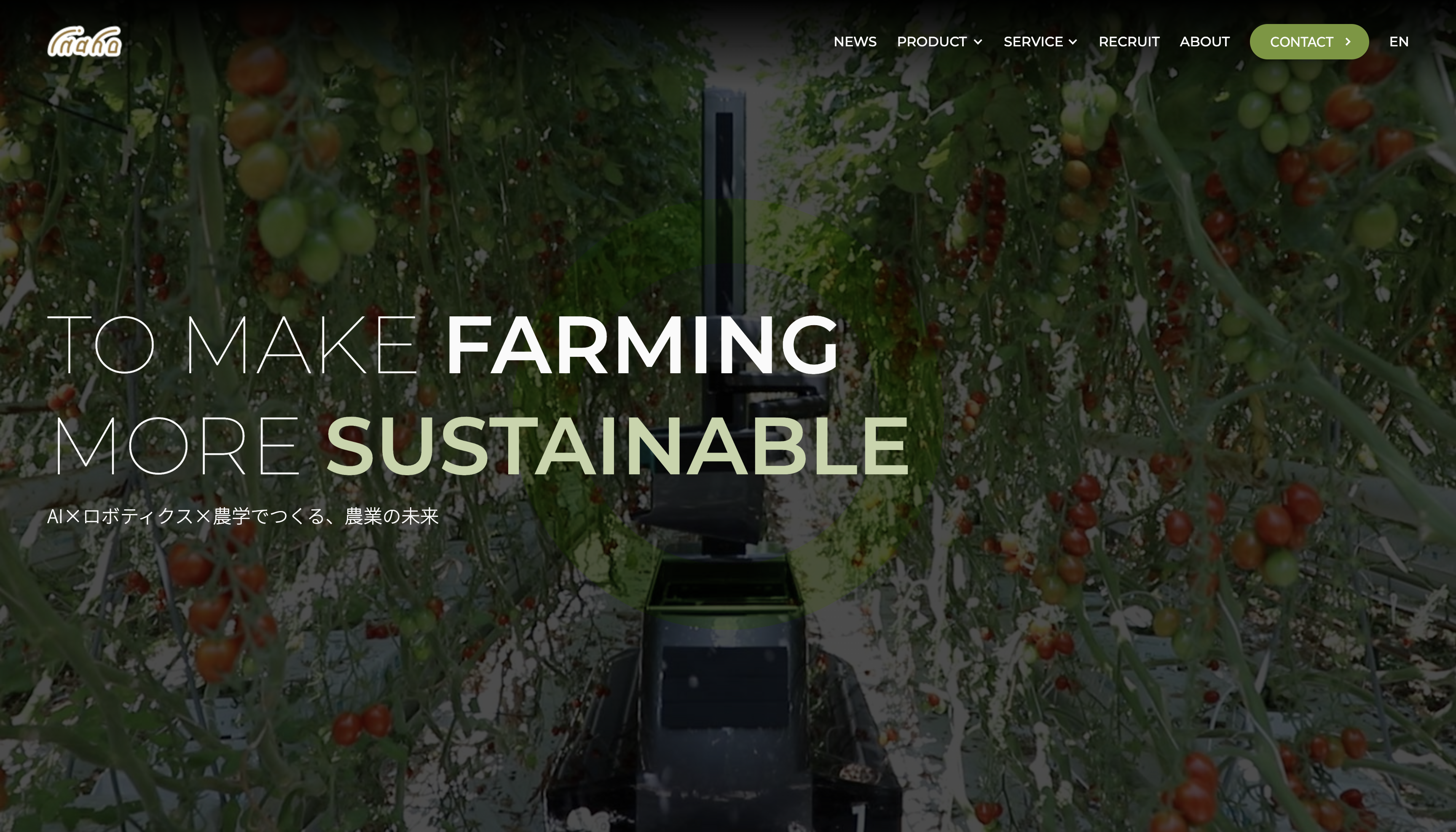
inaho株式会社は、2017年に設立された神奈川県発のアグリテックベンチャーで、アスパラガスやトマト向けのAI自動収穫ロボットを開発しています。
カメラとAIによる画像認識で収穫適期の作物を判別し、ロボットアームで自動収穫することで、収穫作業の省力化や人手不足の解消を目指しています。
収穫量や位置情報など、ロボットが取得する各種データはクラウド上で分析され、圃場ごとの生産性把握や収量予測など、生産の高度化に活用されつつあります。
将来的には、こうした予測結果を作業計画や経営判断にフィードバックするなど、より高度なデータ活用も視野に入れています。
クボタ

クボタは、農業機械とICTを組み合わせたスマート農業ソリューションを展開しています。
自動運転対応のトラクターや田植機、農薬散布ドローンなどに加え、営農支援システム「KSAS(クボタスマートアグリシステム)」を通じて、圃場ごとの作業履歴や収量・品質データをクラウド上で一元管理し、データに基づいた栽培計画や作業指示を可能にしています。
これにより、重労働だった作業の負担軽減や、作業のムラ・漏れの抑制、燃料・資材の無駄の削減が期待されており、実際に圃場管理の効率化や収量・品質の向上が報告されています。
機械とクラウド型の営農支援システムをセットで提供することで、日本各地でスマート農業の導入を後押ししている事例と言えます。
参考: スマートアグリソリューション | イノベーション | 株式会社クボタ
デンソー

デンソーは、自動車部品の開発で培ったセンシング・制御技術を農業分野に応用し、主に施設園芸向けの環境制御ソリューションを展開しています。
温室内外に設置したセンサーで温度・湿度・CO₂濃度などを計測し、そのデータに基づいて換気窓やカーテン、暖房機などを自動制御するシステムにより、作物が育ちやすい環境を安定的に維持することを目指しています。
また、農研機構や大学、海外の栽培研究機関などと連携し、果実収穫ロボットにおける画像認識や、温室内の環境・生育データの解析にAIやデジタルツイン技術を活用する取り組みも進めています。
土壌センサーや各種環境センサーで計測したデータをもとに、灌水制御や栽培計画の高度化、病害リスクの早期検知など、データ駆動型のスマート農業の実現を狙っています。
参考: 就農人口不足と食糧危機に立ち向かう、全自動収穫ロボット「Artemy®」の可能性|DRIVEN BASE(ドリブンベース)- デンソー
農業AI導入のメリット
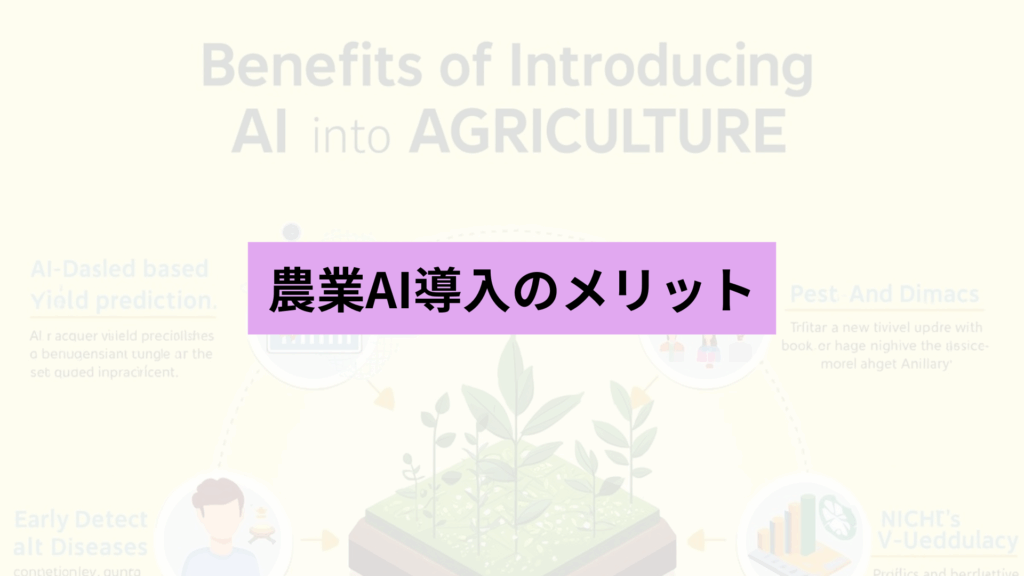
農業分野にAI技術の導入が広がることで、実際に訪れるメリットはなんでしょうか?
実は、未だ一般的な普及こそしていないものの、従来の経験則や勘頼みの栽培管理から、データ駆動型の科学的アプローチへと転換が徐々に進んおり、農場をAIによって最適管理できるようになってきました。
現代の少子高齢化や人手不足が深刻化するなか、AIは労働力不足の緩和や熟練技術の継承支援にも役立ちます。
本節では、農業AI導入によってもたらされるメリットを、3つの観点から解説します。
労働者の負担を減らす
AI技術の導入によってもたらされる最大のメリットの一つに「労働者の負担減」が挙げられます。
これまで人手に頼っていた単調作業や重労働を自動化し、体力的・精神的負担を大幅に軽減できるため、農家の仕事へのハードルが下がったり、本来集中したかったタスクに意識を向けやすくなってきます。
例えば、画像認識と連動した無人除草ロボットは雑草をピンポイントで除去し、腰をかがめての手作業を削減したり、ドローンによる薬剤散布で広大な圃場を短時間で効率的に管理することも可能です。
結果として、作業ミスや事故リスクも低減し、より安全で快適な労働環境の実現につながります。
生産コストの大幅削減
AIによるデータ分析や自動化技術を活用することで、無駄なコストを根本から削減することも可能です。
これは、土壌センサーや気象データを組み合わせた予測モデルにより、肥料や農薬の適正投与量を算出するなどの「数値予測」が容易になるためです。これにより従来の一律散布と比べ、資材コストを削減できるようになります。
AIによる需要予測と在庫管理により収穫量を適正化も、過剰生産や廃棄を抑制することにつながります。
トータルの生産コストを大幅に引き下げ、経営の安定化につなげられ繋げられるという点で、AIは会計的にも優しい存在になり得ると言えるでしょう。
人的リソースの最適化
AIの使用は、単純作業から人間を解放すると言っても過言ではありません。さらに、近年のAI技術では高度な判断が必要な業務までカバーすることができるようになってきました。
つまり、AIの活用は人的リソースの適材適所配置を支援してくれるのです。
また、新規スタッフのトレーニングもAI教材やAIチャットボットで効率化し、人材育成コストを抑制するといった例も考えられます。
これは事例として有名なものがあるとはいえませんが、今後は「作業以外の価値創造」においてもAIが活躍していくことは間違い無いでしょう。
農業AI導入のデメリット
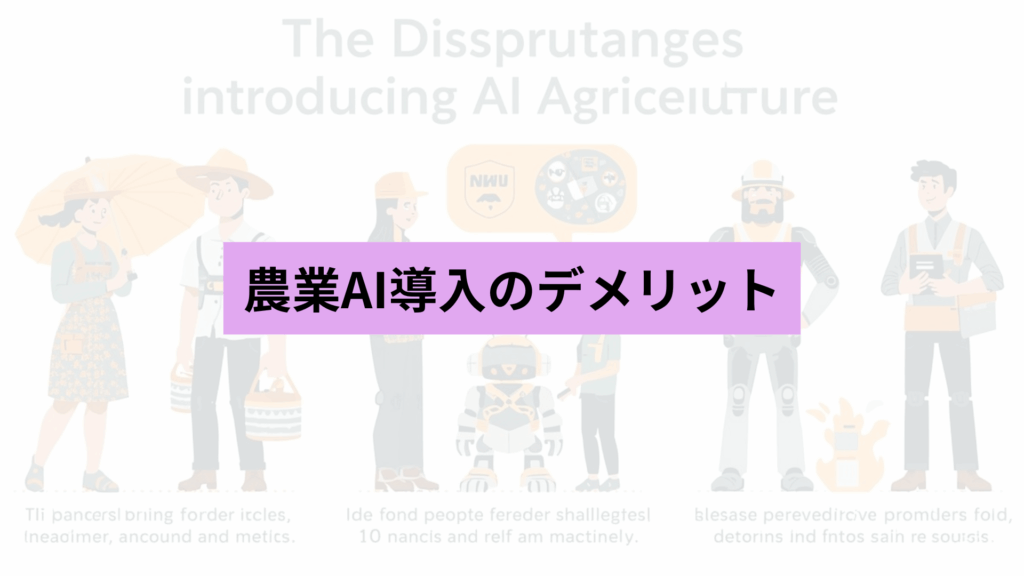
農業AIの導入・活用は効率化や省力化を実現する一方で、導入に伴う課題も少なくありません。
コストの高さはもちろんのこと、専門人材の育成や運用サポート体制の整備が必要になる場合もあります。
これらのデメリットをそのまま放置すると、想定以上の運用負荷やトラブル対応に悩まされることになります。
本節では、具体的なデメリットを2項目に分けて詳しく解説します。
農業AI導入コストの負担
農業AIを導入する際、最大の壁となるのが初期費用の高さです。
高性能カメラやセンサー、ドローン、自動運転機器など、ハード面だけで数百万円単位の投資が必要になることも想定されます。
イニシャルコストが低くても、ソフトウェアのライセンス費用や保守・アップデート費用も継続的に発生するので、小規模農家にとっては大きな負担となるでしょう。
近年は分割払いやリース契約、国や自治体の補助金制度を活用する事例も増加していますが、資金調達計画を十分に練った上で導入を検討することが重要です。
農業AI人材の育成コスト
農業AIの導入にはハード・ソフト面のコストだけでなく、人材育成にも多額の投資が必要なる場合があります。
サービスとして普及が進むAIは、AIやデータ分析の知識に明るくない人でも扱えるようなものになるはずですが、現状、内製化を前提としたAI活用が求められています。
そういった場合、AIモデルの基本的な仕組みや知識を習得させるには、セミナー参加費やeラーニング受講料、社内研修の講師人件費などがかさむ可能性も考慮しましょう。
こうしたコスト負担を軽減するには、国・自治体の助成金活用や農業関連大学との産学連携、オンライン教材の積極的活用が有効です。
まとめ
本記事では、多様な視点から農業AIの活用方法を解説し、海外10社と国内9社の先進事例を取り上げました。
AIの活用は一次産業における課題を解決する事例がある一方、必ずしもメリットのみを享受できるわけでは無いことに留意が必要です。
各種情報を適切に判断していくことをお勧めいたします。
この記事の著者

児玉慶一
執行役員/ AI・ITエンジニア
愛称: ケーイチ
1999年2月生まれ。大学へ現役進学後数ヶ月で通信キャリアの営業代理店を経験。営業商材をもとに100名規模の学生団体を構築。個人事業主として2018年〜2020年2月まで活動したのち、2020年4月に広告営業事業を営む株式会社TOYを創業。同時期にITの可能性を感じプログラミングを始め、現在はITエンジニアとして活動中。2021年にLeograph株式会社に参画し、AI研究開発やWebアプリ開発などを手掛ける。 「Don't repeat yourself(重複作業をなくそう)」「Garbage in, Garbage out(無意味なデータは、無意味な結果をもたらす)」をモットーにエンジニア業務をこなす。
【得意領域】
業務効率化AIモデル開発
事業課題、戦略工程からシステム開発
Webマーケティング戦略からSaaS開発