AIの異常検知アルゴリズムとは?事例やPythonライブラリを解説!
我々の住む日本の基幹産業である製造業。そんな製造業ですが、昨今の人材不足や生産性向上が叫ばれる中、各種現場では「異常検知AI」の導入・開発が属人的な業務からの解放であると推し進められているのはご存知でしょうか?
本記事では、AIを活用した異常検知アルゴリズムの基礎から最新の手法まで詳しく解説します。具体的な導入事例を通じて実用性を示し、Pythonライブラリを用いた実装方法も紹介。
異常検知技術の理解を深め、ビジネスへの応用に役立てたい方に最適な内容となっております。
AI異常検知の仕組み
具体事例などに移る前に、まずは「そもそもAI異常検知とはどんな仕組みなのか」について解説していきたいかと思います。
前置きしておくと、その仕組みは非常に数学的アプローチが多く使われていて、専門用語が多く出てくるので、適宜調べるなどして参考程度に見ていただけると幸いです。
外れ値を検出する(ホテリング理論)
ホテリング理論とは、多変量のデータにおける外れ値検出に有効な統計手法です。データセット全体の共分散構造を考慮し、各データポイントが平均からどれほど離れているかを評価します。
具体的には、ホテリングのT²統計量を用いて各観測値の異常度を算出し、閾値を超える点を外れ値として識別します。これにより、単一の変数だけでなく、複数の変数間の相関関係を維持しながら異常を検出することが可能です。
ホテリング理論は、製造業における品質管理や金融分野での不正検出など、様々な応用分野で効果的に活用されています。その精度の高さと汎用性から、AI異常検知アルゴリズムの基盤として広く利用されています。
情報の属性を分析する(クラスタリング)
クラスタリングとは、データの属性をグループ化することで異常検知を行う手法です。
主なアルゴリズムとして、K-meansやDBSCAN、階層的クラスタリングなどが挙げられます。それぞれ特徴が違えど、どれもデータを類似性に基づいて複数のクラスタに分割するアルゴリズムです。
通常のデータポイントは既存のクラスタに適切に配置されますが、異常なデータポイントはどのクラスタにも属さないか、非常に小規模なクラスタに分類されます。
例えば、製造業では製品の品質データをクラスタリングし、正常範囲から逸脱したデータを早期に検出することで不良品の発生を防止します。これは前項での「外れ値検出」と若干似ているアプローチではあります。
また、金融分野では取引データをクラスタリングすることで、不審な取引パターンを識別し、不正行為の防止に貢献することも可能です。
クラスタリングによる異常検知は、多次元データの複雑な関係性を考慮できる点で有効ですが、適切なクラスタ数の設定やノイズへの対応が課題となることもあります。
AI異常検知のアルゴリズム一覧
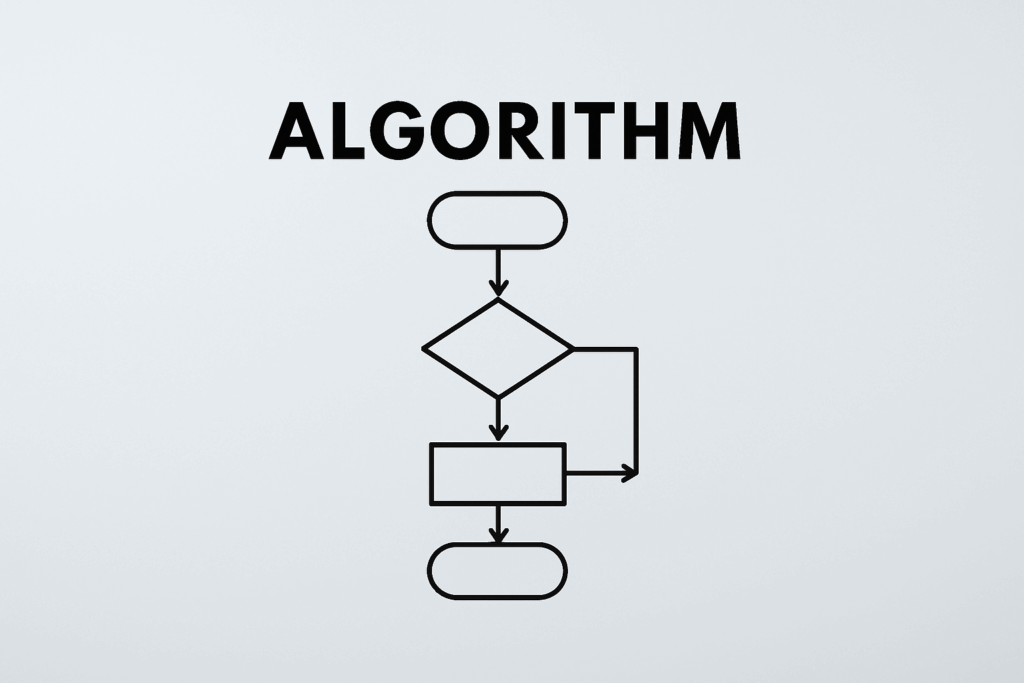
では、ここからはAI異常検知に使われている代表的なアルゴリズムについてご紹介します。
どれも優れたアルゴリズムで、様々な現場で採用されている信頼のおけるものとなっています。
Isolation Forest
Isolation Forest(アイソレーションフォレスト)は、2008年にFei Tony Liu氏らによって開発された異常検知アルゴリズムで、主に高次元データセットの異常検出に特化しています。
機械学習を勉強し始めたエンジニアにとっては最も親しみの深い「決定木」という予測分析手法を用いています。
この手法では、データポイントをランダムに分割する決定木を多数構築し、各ポイントがどの程度早く「隔離」されるかを基に異常度を評価します。 正常なデータは多数のデータと類似しているため、隔離に時間がかかる一方、異常なデータは少数であるため迅速に隔離されます。
この特性を活かし、Isolation Forestは計算効率が高く、高次元データにも適用可能です。また、パラメータ設定が比較的簡単であり、大規模なデータセットにもスケーラブルに対応できます。
Local Outlier Factor
Local Outlier Factor(LOF)は、2000年にM. M. Breunigらによって提案された異常検知アルゴリズムです。
この手法は、各データポイントの局所密度を評価し、周囲のデータポイントと比較して異常度を算出します。具体的には、各ポイントのk近傍距離を基に、密度比を計算し、高いスコアを持つ点を外れ値として識別します。
LOFはデータの局所的な構造を考慮するため、密度が変動するデータセットにおいても効果的に異常を検出できます。異なる密度を持つクラスタ間での外れ値検出にも強みを持ちます。
LOFは非パラメトリックな手法であるため、事前にデータの分布を仮定する必要がなく、柔軟性に優れています。Pythonのscikit-learnライブラリなどで実装が提供されており、実務においても容易に導入可能です。
DBSCAN
DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)は、1996年にMartin Esterらによって提案されたクラスタリングアルゴリズムです。
DBSCANでは、データポイントの密度に基づいてクラスタを形成し、密度が低い領域に位置するデータを異常値として識別します。各ポイントのε近傍内の点数を評価し、十分な点数を持つ点をコアポイントとしてクラスタの基盤としているため「Density-Based」という名前がついているんですね。
このアルゴリズムは非線形な分布や異なる密度を持つクラスタに対しても柔軟に対応可能であり、形状に依存しないクラスタリングが実現できます。また、ノイズ耐性が高いため、実データにおける外れ値検出にも有効です。
一方で、適切なε(近傍の半径)とMinPts(最小ポイント数)の設定が難しく、大規模データセットでは計算コストが増加するという課題も存在します。
このアルゴリズムはPythonのscikit-learnライブラリを用いることで、DBSCANの実装が容易に行え、実務での活用が促進されています。
Gaussian Mixture
Gaussian Mixture(ガウシアンミクスチャー)モデルは、複数の正規分布を組み合わせてデータ全体の分布を表現する確率モデルです。データが複数の潜在クラスターに属していると仮定し、各クラスタを個別のガウス分布でモデル化します。
異常検知においては、各データポイントがいずれのガウス分布にも高い確率で属さない場合を異常と判断します。
具体的には、期待値最大化(EM)アルゴリズムを用いてモデルのパラメータを推定するというイメージです。
また、確率的アプローチにより、異常スコアを定量的に評価できる点も利点です。 リスクとしては、ガウス分布の仮定がデータに適合しない場合、モデルの性能が低下するといった特徴を持っていることです。
One‑Class SVM
One‑Class SVM(ワンクラスサポートベクターマシン)は教師なし学習の手法で、正常データの分布を学習し、その分布から大きく外れるデータポイントを異常として識別します。
データを高次元空間にマッピングし正常データを囲む境界を構築して、この境界から外れるサンプルは異常と判断されます。
One‑Class SVMを使う利点は、他のアルゴリズム同様に高次元データや非線形なデータにも対応可能であり、複雑なデータ構造を効果的に捉える点にあります。
一方で、パラメータの選定(カーネルの種類や正則化パラメータ)がモデル性能に大きく影響するため、チューニングが必要となります。ここには専門的な知見と業務現場との連携が必須であるため、容易ではありません。
また、One-ClassSVMもPythonのscikit-learnライブラリに標準装備されており、クラスを呼び出すことで簡単にプログラムを実装することができます。
製造業の品質管理においてはベアリングの異常音を検知するシステムにOne‑Class SVMが適用されています。
ABOD
ABOD(Angle-Based Outlier Detection)は、データポイント間の角度情報を活用して外れ値を識別する異常検知手法です。各データ点に対して他の点との角度を計算し、その分布を分析することで異常を検出します。
正常なデータ点は一貫した角度パターンを示すのに対し、異常な点は不規則な角度を持つため、これを基に外れ値として分類されます。
ABODは非線形な分布にも対応可能であり、多様なデータセットに適用しやすい特徴があります。
PythonにおいてはpyodライブラリがABODをサポートしており、実装が可能です。
Prophet
Prophet(プロフェット)は、Facebook(現Meta)が開発した時系列予測ライブラリであり、異常検知にも効果的に利用されています。シンプルなモデル構築を可能にし、季節性やトレンドの変動を柔軟に捉えることができます。
FacebookのAI研究は世界のテック企業の中でもトップレベルに盛んに行われており、そのうち信頼のおけるアルゴリズムライブラリの一つと言っても過言ではありません。
Prophetは、欠損値や外れ値に対する耐性が高く、実データにおける異常検出に適しています。 時系列データに基づいて予測値を生成し、観測値との乖離を分析することで異常を識別します。
予測モデルがデータのパターンを正確に反映している場合、異常な変動は明確な差異として現れるため、高精度な異常検出が実現できます。
主な利点は、ユーザーが容易にパラメータを調整できる点や、複雑な季節性を考慮したモデル構築が可能な点です。
また、PythonおよびRで利用可能なため、多様な開発環境で活用できます。
Matrix Profile
Matrix Profile(マトリックスプロファイル)は、時系列データにおけるパターン探索および異常検知に優れた手法です。
対象となる時系列データ内のすべてのサブシーケンス間の類似度を効率的に計算し、各サブシーケンスに対する最も近い類似パターンとの距離をプロファイルとして可視化します。異常なデータポイントは、このプロファイル上で通常よりも高い距離値として現れるため、容易に識別することが可能です。
計算の高速性とスケーラビリティの点においてMatrix Profileは優位なポジションにあるといえます。大規模な時系列データセットに対しても効率的に適用でき、多様なウィンドウサイズに対応することで、異なるスケールのパターン検出が可能です。
また、アルゴリズム自体がシンプルでありながら強力な分析能力を持つため、複雑な前処理やモデル構築を必要とせずに高精度な異常検知を実現します。
もちろんPythonにおいてもライブラリ(matrixprofile)が提供されています。
AI異常検知の導入事例5選!
ここまでAI異常検知についての概論を解説してきましたが、本節からは実際にどんな事例があるのかをご紹介します。
ここで出てくる事例に共通するキーワードは「生産性向上」「業務効率化」です。そこに注視しながら読み進めていただくと良いかもしれません。
トヨタ自動車

トヨタ自動車は、生産現場における異常検知にAI技術を積極的に導入していて、車の製造ラインに設置された各種センサーから収集される大量のデータをリアルタイムで解析し、機械の異常や製品の品質不良を早期に検出する仕組みを構築しています。
作業員の負担軽減と効率化を目的として、部品を自動で運ぶ機械の研究開発を行っていたり、目視検査をAIで自動化するプラットフォームを自社開発したりなど、作業効率化と健康安全面の改善を行っているようです。
これらの取り組みにより、故障の予兆を事前に把握し迅速な対応が可能となるため、ダウンタイムの削減や生産効率の向上に寄与しています。
キユーピー

キユーピー株式会社は、製造プロセスにおける品質管理の高度化を目指し、AI異常検知技術を積極的に導入しています。
具体的には、製造ラインに設置された高精度センサーから収集される膨大なデータをリアルタイムで解析し、製品の品質不良や設備の異常を早期に発見するシステムを構築しています。
2016年リリースによると、AI開発で有名なブレインパッド社との共同開発により、食品工場における不良品の検知をディープラーニングによる画像解析で行う取り組みをしています。
私たち消費者がより安全な食品を手にするためにも、異常検知技術は役に立っているのです。
SUBARU

SUBARU株式会社は、自動車製造における品質向上と生産効率の最適化を目的として、AI異常検知技術を積極的に導入しています。
トヨタと同じく車の製造において異常検知技術は不可欠なものと言っても過言ではありません。
例えば、同社の群馬にある工場ではAIでカムシャフト品質を全数保証するシステム構築を富士通が支援していたりなど、不良品の発生を未然に防ぎ、製品の品質と信頼性を高めています。
ブリヂストン

ブリヂストン株式会社は、タイヤ製造における品質管理と生産効率の向上を目指して、AI異常検知技術を積極的に導入しています。
具体的には、生産ラインに設置された各種センサーから収集される膨大なデータをリアルタイムで分析し、製造過程で発生する異常や不良品を迅速に検出するシステムを構築しており、このICT工場の取り組みによりタイヤ成型工程の生産性を2倍にするなどの功績を上げています。
さらに、ブリヂストンはIoTセンサー技術の研究開発にも注力しており、2017年に1月にはデジタルソリューションセンターを設置し、2019年にはモビリティ領域のデジタルデータに強いオランダの企業を買収したりなど、現場への技術浸透を積極的に進めているようです。
花王

花王株式会社もまたAI異常検知技術を積極的に導入しています。
AI技術を導入したプラントの異常予兆検知の取り組みが有名な事例で、大幅な業務負荷削減に加えて生産性向上、属人化の解消を達成しました。
化学消費財のメーカーということもあり、その業界基準を満たす製造は簡単なものではありません。
それを達成するために今まで人的リソースに頼っていたところを、花王は独自の知見を活かして解決しているのです。
AI異常検知を作れるPythonライブラリ3選
事例紹介では大手企業の名前がずらりと並んでいて、「AI異常検知」と聞くと、一見すると大資本でないと実現が難しいものなのではないか、そんなふうに感じてしまうかもしれません。
しかし、実のところそんなことはありません。
Pythonという人気なプログラミング言語には豊富なAI異常検知を実現しうるライブラリが揃っています。本節では代表的なものを3つご紹介します。
Tensorflow
本サイトの記事に度々登場する超有能ライブラリ、Tensorflow。筆者もことあるごとにこのライブラリを使っています。
TensorFlowは、Googleによって開発されたオープンソースの機械学習ライブラリであり、深層学習モデルの構築に優れた柔軟性を提供します。
AI異常検知においては、ニューラルネットワークを活用した高度なモデルを容易に設計・訓練することが可能です。Kerasとの統合により、複雑なデータパターンの学習やリアルタイムでの異常検出が実現できます。
また、TensorFlowは大規模なデータセット処理に強く、分散コンピューティング環境でも効率的に動作します。
ドキュメントや各種プログラミング言語のクライアントも充実しているため、非常にエンジニアフレンドリーなライブラリと言っていいでしょう。
チュートリアルも充実しており(ドキュメントやJupyter Notebook、公式YouTube解説など文字通り充実)、このライブラリによって助けられているという開発現場も少なくないはずです。
scikit-learn
こちらも本サイトでは常連のライブラリ、scikit-learnはPythonで広く利用されているオープンソースの機械学習ライブラリで、AI異常検知においても高い評価を得ています。使いやすいAPIと豊富なアルゴリズム群により、初心者から専門家まで幅広いユーザーに適しています。
本記事の冒頭で解説したアルゴリズムのほとんどがこのscikit-learnのクラスに標準で定義されており、機械学習界隈では安定のライブラリです。
SciPy
SciPyは科学技術計算において広く利用されています。
高度な数値計算機能(クラス、メソッド)を提供しており、特に統計解析や最適化、信号処理などの分野で強力なツールを備えています。
AI異常検知においては、データの前処理や特徴抽出、統計的手法の実装において役立ちます。 つまり、このライブラリでアルゴリズムを構築するというより、事前データ処理での優秀なサポート役といった感じでしょうか。
まとめ
製造業はこれがなければ日本経済は成り立たない、そんな言い方でも全く過言ではありません。
そんな製造業を支える技術にはもちろん人による職人的なナレッジがありますが、それを支えるテック領域も見逃せはしません。
この記事の著者

児玉慶一
執行役員/ AI・ITエンジニア
愛称: ケーイチ
1999年2月生まれ。大学へ現役進学後数ヶ月で通信キャリアの営業代理店を経験。営業商材をもとに100名規模の学生団体を構築。個人事業主として2018年〜2020年2月まで活動したのち、2020年4月に広告営業事業を営む株式会社TOYを創業。同時期にITの可能性を感じプログラミングを始め、現在はITエンジニアとして活動中。2021年にLeograph株式会社に参画し、AI研究開発やWebアプリ開発などを手掛ける。 「Don't repeat yourself(重複作業をなくそう)」「Garbage in, Garbage out(無意味なデータは、無意味な結果をもたらす)」をモットーにエンジニア業務をこなす。
【得意領域】
業務効率化AIモデル開発
事業課題、戦略工程からシステム開発
Webマーケティング戦略からSaaS開発



