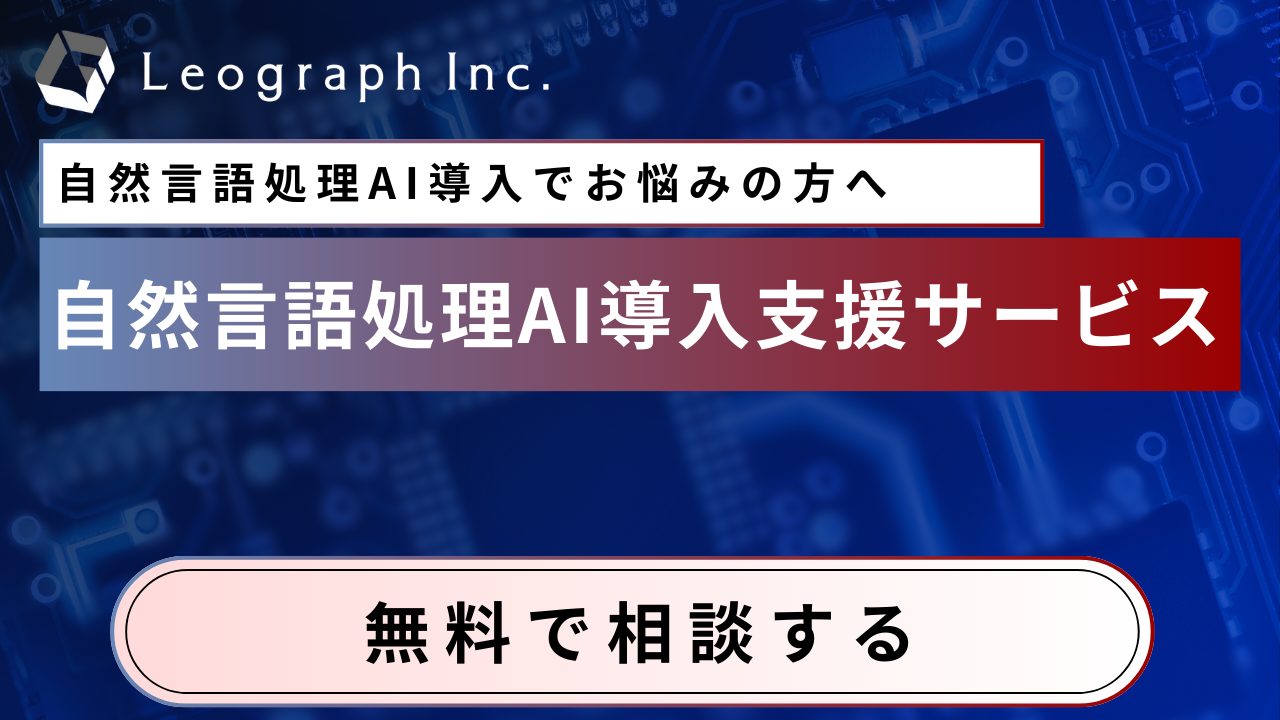金融業のAI活用事例5選!AIで銀行はなくなってしまうのか!?
AI技術の進化に伴い、金融業界でも融資審査やカスタマーサポート、自動会計、生成AIまで幅広く活用が進んでいます。
まずはAI活用の基礎を抑え、その応用範囲を広く把握していきたいところですね。
本記事では、主要なAI活用領域を解説し、リスクを整理していきます。さらに、AI導入によって業務がどう変化するかを事例とともに詳しくご紹介いたします。
この記事を読むと、AI活用による業務効率化やコスト削減の実態を把握できるだけでなく、自社導入や投資判断のヒントも得られます。
金融業でのAI活用とは?
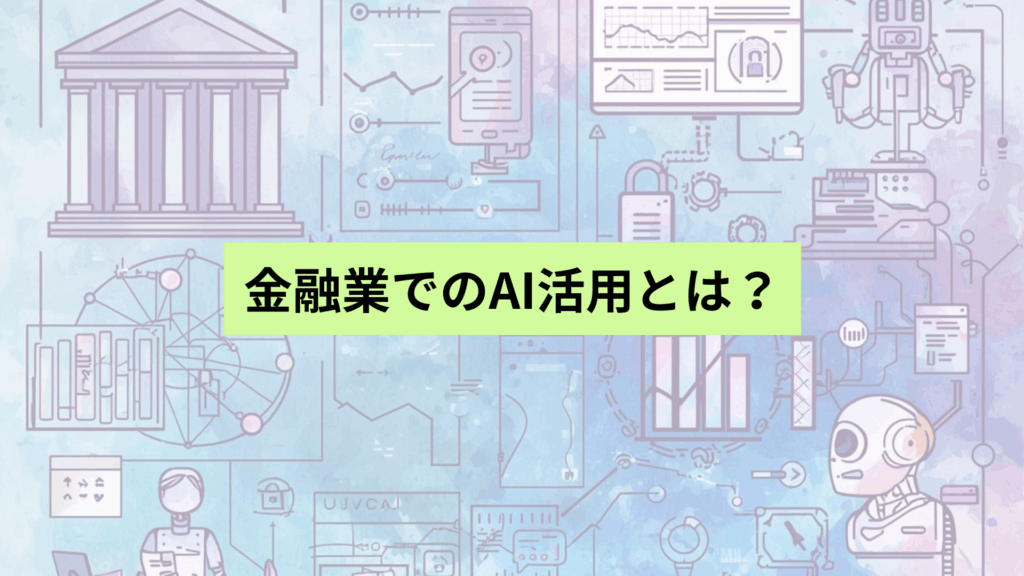
金融業界では膨大な取引データや顧客情報を的確に処理し、リスク評価や業務効率を高めるためにAIが欠かせない存在となっています。
従来は人手に頼っていた複雑な審査や問い合わせ対応、帳票作成といった業務も、AIの登場で精度やスピードが大幅に向上しました。
また、顧客に応じてパーソナライズサービスを実現し、顧客満足度の向上に直結することもマストとなってきています。
本節では、特に注目度の高い4つのAI活用領域を概観していきたいかと思います。
融資審査での活用
融資審査プロセスでは、AIが顧客データや取引履歴をリアルタイム解析し、従来のルールベース審査を大きく進化させています。
金融業界は、これまでは与信のスコアや信用力を人手によって判断していたものの、昨今の人手不足・AI市場の顕在化によってAI導入を余儀なくされてきました。
その点、AIモデルによるスコアリングで信用力を多面的に評価したり、審査時間を数日から数分に短縮することが可能になりました。ケアレスミスやバイアスの排除も実現され、業務負担が大幅に減らされることは間違い無いでしょう。
銀行はこうしたAI技術を活用し、迅速かつ公正な審査体制を構築し、顧客満足度の向上と与信リスクの抑制を同時に達成しています。
カスタマーサポートでの活用
AIチャットボットと自動音声応答(IVR)を組み合わせることで、24時間365日の問い合わせ対応が可能になります。
銀行や証券会社は、この技術を使うことでFAQ照合や手続き案内を的確に行い、応答速度と正確性を大幅に向上させることが可能になります。
さらに、過去の問い合わせ履歴や顧客属性をもとにパーソナライズされた提案を自動生成することも可能になります。
もし、顧客がAIによる対応だけでは満足がいかない場合にも、AIが提案する対応策を元にオペレーターが迅速介入することで、トラブルの長期化を防ぎ、信頼性の高いサポート体制を構築できます。
会計の自動化
AIの強みは、膨大なデータを短時間で読み込み・出力することができる点です。
会計においては自動仕訳や経費精算を実行します。さらに、OCR連携により紙請求書や領収書をデジタル化し、項目抽出から勘定科目への振り分けまでをRPAが担うため、入力ミスや二重計上を大幅に削減することが可能になります。
リアルタイムにキャッシュフローを可視化し、未来の収支予測やシナリオ分析も可能となるため、融資の際の判断がAIドリブンになることが予想されています。
つまり、これまでは人間のベテラン“のみ”が担っていた業務領域を、AI導入によって技術が民主化されていくという流れが金融業界では起きているのです。
生成AIの活用
生成AIは、高度なレポートや文書を自動生成することが可能です。
銀行では投資分析レポートや市場動向レポートを作成する必要があるため、生成AIの導入はアナリストの工数を大幅に削減することに繋がり、結果的に業務負担を限りなく減らすことが可能となるでしょう。
金融業でのAI活用の課題はある?
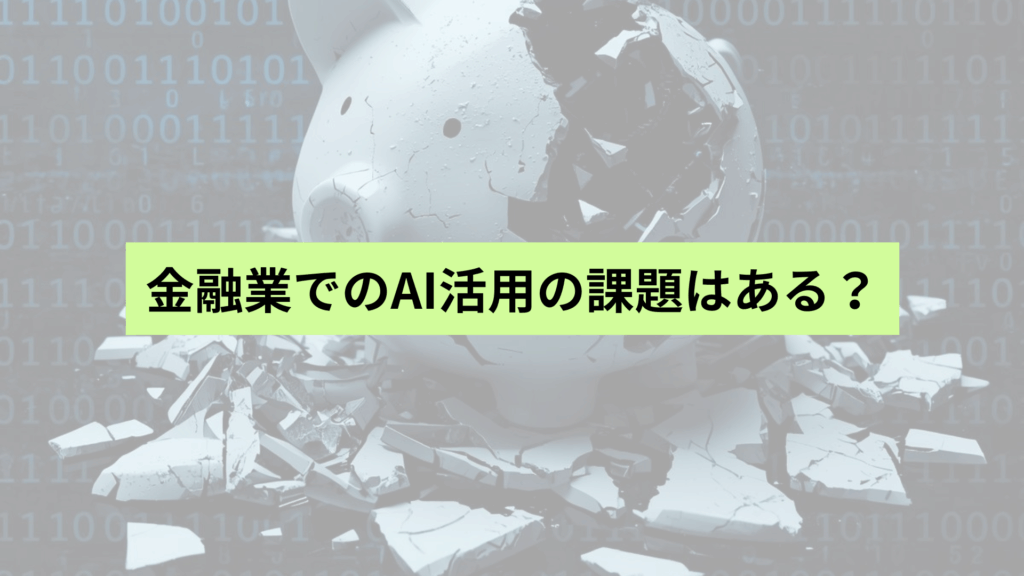
AIを金融業務へ取り入れることは、多くのメリットを享受できます。
しかし実運用には多岐にわたる課題が存在します。
膨大な顧客データを扱ううえで必要なセキュリティ対策や個人情報保護、法規制遵守の厳守は必須ですし、データの偏りによる判定の公平性低下も無視できません。
本章では、「セキュリティの課題」と「雇用の不安定化」を中心に、金融業でのAI導入に立ちはだかるハードルを整理します。
セキュリティの課題
金融業界では膨大な顧客資産情報と機密データを扱うため、AI導入時のセキュリティ対策が最優先です。
まず、個人情報を含む1次情報をもとにAIモデルを構築する際には、学習データや推論結果の暗号化保存、アクセス制限、権限管理を徹底し、覗き見や不正取得を防止する必要があります。
定期的なペネトレーションテストやモデルの堅牢化、インシデント対応フローの整備が欠かせません。
自社で構築をしなくとも、もし外部ベンダーが提供するAIサービスを利用する際には、委託先のセキュリティ基準やSLAの確認、サードパーティ監査の実施が重要です。
これらをクリアしてこそ、顧客信頼の担保と法規制遵守を両立できると言えるので、すなわち「個人のクリティカルなデータを大量に抱える金融業界」に取って、セキュリティ課題は立ちはだかる壁になるでしょう。
雇用の不安定化
AIの導入で、定型的な事務作業やデータ分析業務は効率化が進むことは間違えようのない事実です。
しかし、その一方でオペレーターや審査担当など従来の業務が削減され、雇用機会が減少する恐れがあります。
特に中堅・若手社員はスキルや経験がAIに置き換えられやすく、キャリアの不透明化や収入減少への不安を抱きやすいでしょう。
こうしたリスクを緩和するには、再教育プログラムやAIリテラシー研修の充実、社内異動によるスキルシフト支援が不可欠です。
金融業でのAI活用でなくなる銀行のお仕事
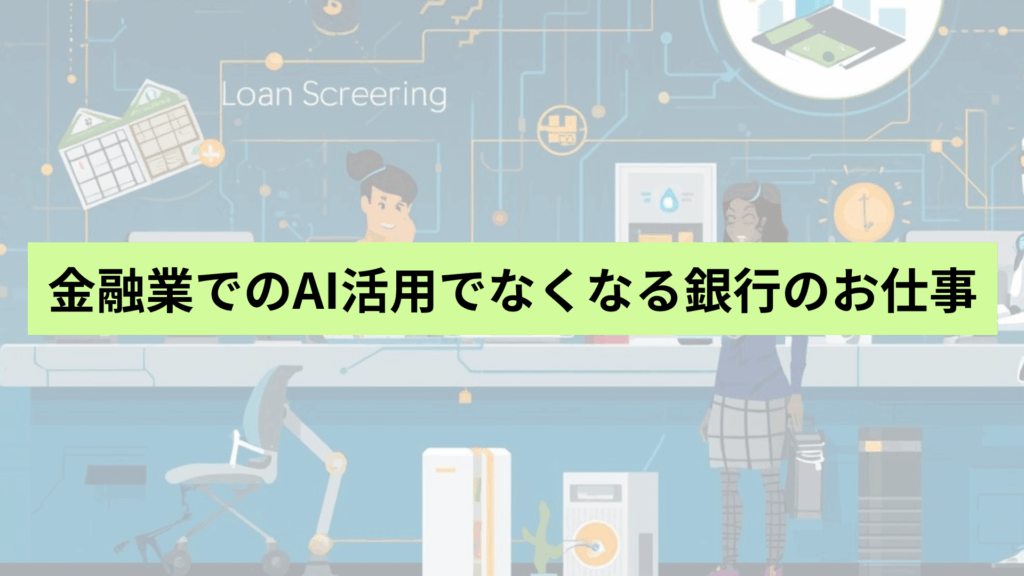
AIの高度化により、銀行業務の多くは自動化と省力化が加速しています。特にルーティン化された事務処理や膨大なデータ分析を伴う審査・査定などは、AIによる効率化の恩恵を最も受ける分野です。
これまで専門スタッフが担ってきたバックオフィス業務や複雑な与信判断が、AIのアルゴリズムによって短時間かつ高精度に実施されるため、これらの職務は徐々に機械へ置き換わる流れが強まっています。
もちろん、完全撤廃には法規制や人間判断の必要性も絡むため、一夜にして消滅するわけではありませんが、今後の銀行は「人 vs AI」の境界線を見極めながら適切な再配置が求められるでしょう。
本節では、具体的に“なくなる”とされる(予想される)業務領域を詳しく見ていきます。
※本節の内容は事実を断定するものではないため、あらかじめご了承の上ご覧になってください。
バックオフィスなどの事務処理
バックオフィス業務は請求書発行や入金確認、経費精算など定型的な事務作業が中心になってきます。
これらはルールベース(決まった業務フロー)の自動化とOCR×RPAの組み合わせで、大量処理を短時間でこなせるようになっています。
ここに、AIチャットボットによる問い合わせ対応や機械学習モデルでの異常検知も加わり、ヒューマンエラーの削減とコスト圧縮が実現できる点が“経営判断としては魅力的”と言えます。
結果として、人手は例外対応や戦略的データ分析へシフトし、バックオフィスの役割が“サポート”から“価値創出”へと進化していくと言われているため、前述のような領域に多くの人間が雇用され続ける未来はないと言っても過言ではないでしょう。
審査・査定の業務
審査・査定業務では、機械学習モデルが顧客の口座取引履歴や消費行動データ、信用情報を多角的に解析し、与信スコアやリスク評価を瞬時に算出していくことが可能になります。
NLP技術(自然言語処理)を活用すれば、財務諸表や契約書類の自動読み取り・要約も可能となり、書類チェックに要する時間を大幅に短縮。
これにより、融資可否判断や保険契約の査定が従来の数日から数分単位へと加速するため、やはりこの領域で働く人間の総数も減っていくはずです。
ただし、モデルのブラックボックス化による説明責任やバイアス対策、法令遵守の観点は依然重要となるのも間違いありません。
最終判断には人間のチェックを組み込み、透明性高く運用する体制づくりがAI活用の成功の鍵となります。
金融業でのAI活用事例5選

金融業界におけるAI導入は、すでに審査・査定領域を超え、顧客対応や営業支援、リスク管理など多彩な分野へと広がりつつあります。
本節では、国内の主要金融機関5社をピックアップし、実際の取り組み内容と得られた成果を各社の導入背景や運用体制、実際の効果と今後の展望を具体例とともに詳しく見ていきます。
三菱UFJ銀行
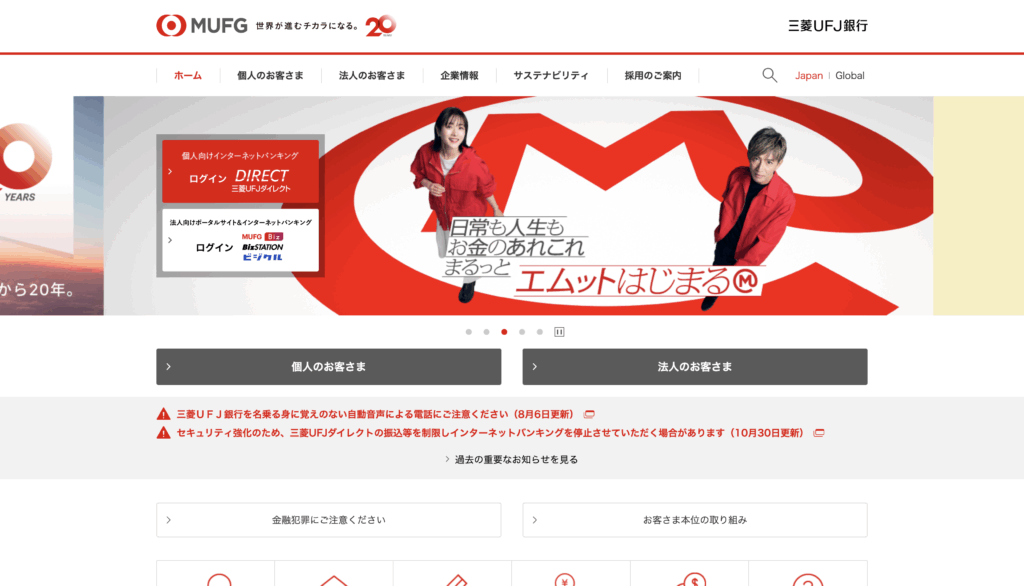
三菱UFJ銀行は、生成AIの積極導入で業務改革を加速しています。
2024年4月に発足した「デジタル戦略統括部」は、全社横断的に営業提案の高度化や社内文書の自動生成など、生成AIを活用した多様なプロジェクトを推進中です。
さらに、2025年4月に次世代AI共通基盤「Databricks」を採用し、行内に散在していた膨大なデータを統合・分析。これにより、不正検知やリスク管理が強化され、業務の自動化や効率化が一段と進展しています。
また、対話型AI「AI-bow」を自社開発し、行員が日々利用。問い合わせ対応やナレッジ共有を円滑にし、現場の業務負荷を大幅に軽減しています。これらの取り組みから、三菱UFJ銀行は金融業界におけるAI活用のパイオニアとしての地位を確立しています。
参考: MUFGがAI Nativeな組織をめざす理由| 三菱UFJフィナンシャル・グループ
大和証券グループ

大和証券グループは、顧客サービス向上と業務効率化を目的にAI技術を導入しています。
AIオペレーターサービスで定型的な電話問い合わせを自動化し、オペレーターは付加価値の高い相談に専念できます。 生成AIチャットはFAQをベースに図表やマニュアルリンクを提示し、多様な質問に対してわかりやすい回答を実現。
加えて、日本マイクロソフト(2025年6月)やSky社(2024年)との提携により、DX推進をさらに加速しています。
これらの取り組みで、大和証券グループは金融業界のAI先駆者として新たな顧客体験と業務革新をリードしています。
参考1: 大和証券と日本マイクロソフトが戦略的枠組み締結。AI エージェント活用で「お客様の資産価値最大化」実現に貢献 – マイクロソフト業界別の記事
参考2: 大和証券グループ本社・大和総研・Sky、資本業務提携契約を締結
SBI証券
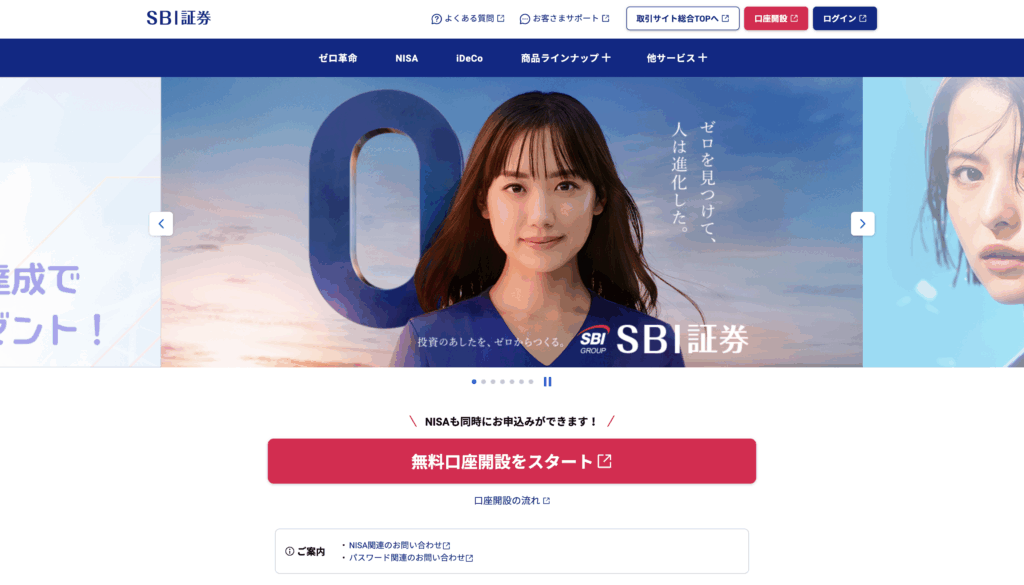
SBI証券は、顧客接点と投資サービスの両面でAIを活用し、ネット証券ならではのデジタルシフトを進めています。
顧客サポート領域では、FAQサイトにAIチャットボット「KARAKURI chatbot」を導入し、24時間365日、口座開設や取引手続きに関する問い合わせに自動対応。営業時間外の問い合わせにも即時回答できる体制を整え、顧客満足度向上と有人対応件数の削減を両立しています。
参考: 困りごとや疑問にも24時間対応、顧客思いのAIチャットボットサービスを実現 – カラクリ株式会社
投資サービス面では、AIを活用した一任運用サービス「SBIラップ AI投資コース」を提供。
市場データや各種指標から抽出した多数の特徴量を機械学習モデルで解析し、市場環境の変化を先読みしてポートフォリオ配分を自動調整することで、同銀行は「正確な将来予測」「冷静な投資判断」「予測モデルの継続的な改善」を目指しています。
損保ジャパン

損保ジャパンはAIを幅広く活用し、業務効率化と顧客満足度向上を両立しています。
カスタマーサポートには機械学習搭載のチャットボットを導入し、24時間365日顧客対応を自動化。問い合わせ内容を高速に解析し、適切な回答や手続き案内を瞬時に提示します。
また、AIによるリスク分析では過去の事故データや気象情報を統合し、損害発生予測モデルを構築。これにより保険商品開発や価格設定の精度を飛躍的に高め、新たなリスクに対応したプランをタイムリーに提供可能です。
さらに、内部業務ではAI-OCRとRPAを組み合わせ、保険金請求書類の読取から支払い審査までを自動化。人的ミスを削減し、年間で数千時間の工数をカットしています。
加えて、AIを用いた画像解析で事故現場や車両の損傷を自動診断し、保険金支払いプロセスを迅速化。被保険者の負担軽減と審査効率向上を両立し、次世代の保険サービスを切り拓いています。
三井住友カード

三井住友カードでは、機械学習を活用したチャットボットを導入し、24時間365日で顧客対応を自動化。
カード利用状況や紛失手続きなどの問い合わせを高速解析し、適切な回答を瞬時に提示、オペレーターの負担を軽減しています。
ビッグデータ分析では、利用履歴や属性データをAIが解析し、最適なキャンペーンやポイント還元プランを自動設計。パーソナライズされた提案により、利用率と顧客ロイヤルティの向上を実現しています。
不正検知では、取引パターンを学習したAIがリアルタイムで異常を検出し、不正利用リスクを低減。さらに、内部業務ではRPAと連携し、請求書処理や入金照合を自動化、年間数千時間の工数削減に成功しています。
まとめ
金融業界ではAI導入により、融資審査からカスタマーサポート、会計処理の自動化や生成AI活用まで、幅広い領域で効率化と品質向上が実現しています。
しかし、セキュリティ強化や雇用への影響といった課題も依然存在します。
事例から学べるのは、AIは銀行を消すのではなく、顧客体験向上と新たな付加価値創出を両立する変革の鍵だということです。
この記事の著者

児玉慶一
執行役員/ AI・ITエンジニア
愛称: ケーイチ
1999年2月生まれ。大学へ現役進学後数ヶ月で通信キャリアの営業代理店を経験。営業商材をもとに100名規模の学生団体を構築。個人事業主として2018年〜2020年2月まで活動したのち、2020年4月に広告営業事業を営む株式会社TOYを創業。同時期にITの可能性を感じプログラミングを始め、現在はITエンジニアとして活動中。2021年にLeograph株式会社に参画し、AI研究開発やWebアプリ開発などを手掛ける。 「Don't repeat yourself(重複作業をなくそう)」「Garbage in, Garbage out(無意味なデータは、無意味な結果をもたらす)」をモットーにエンジニア業務をこなす。
【得意領域】
業務効率化AIモデル開発
事業課題、戦略工程からシステム開発
Webマーケティング戦略からSaaS開発