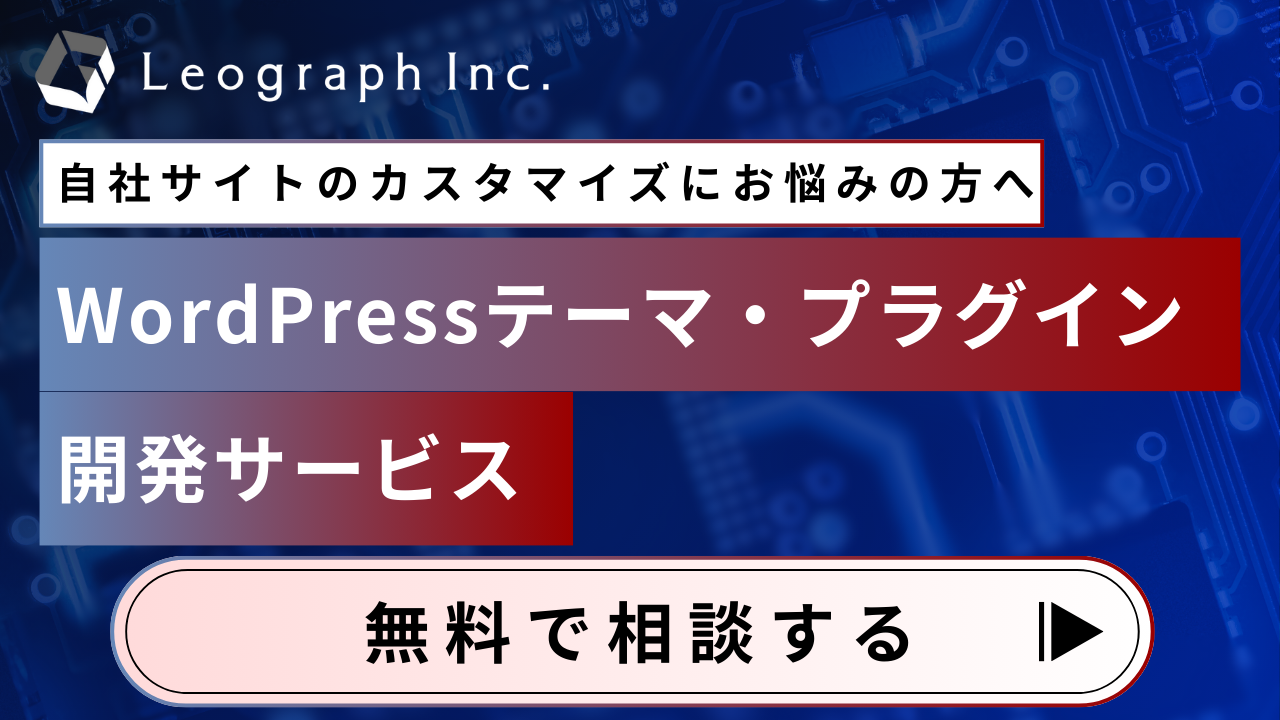【テンプレートあり】WordPress自作テーマの作り方とは?難易度やメリットも解説!
本記事では、WordPressの自作テーマを作る方法を解説していきたいかと思います。
既存テンプレートとの違いやダウンロード可能なベースファイルの活用法、 制作難易度やカスタマイズ性・ブランド一貫性向上などのメリットを整理し、わかりやすく解説していきます。
なお、自作テーマ開発用のベーステンプレートファイルも記載しているので、ぜひデベロッパー環境用にダウンロードしてお使いください。
WordPress自作テーマとは?

WordPress自作テーマとは、WordPressサイトの見た目&ファンクションを自由にデザインし、PHPやHTML、CSSで機能を自前で実装するテーマのことです。
本節では既存テンプレートとの違いと、ベースファイル活用法を解説します。
既存テンプレートとの違い
既存のテンプレート(企業の発行するものや有名なテンプレート)は、あらかじめ設定されたフォルダ構成やCSS、関数の命名規則に縛られ、デザインや機能拡張が部分的にしかできないことが少なくありません。
もちろん、既存テーマをカスタマイズすることもできます。しかし、あらかじめ用意されたルールに則った記述が必要な場合が多く、自社独自の表現が難しくなってしまいます。
特に、細かなレイアウト調整や独自ウィジェットの導入を図ると、無駄なコードやプラグインに頼るケースも。 そのて、、自作テーマなら、HTMLやPHP、CSSの記述ルールを自分流に設計でき、動的処理やテンプレート階層も自由自在です。
【ダウンロード可】自作テーマのベースファイル
自作テーマの第一歩として、最小限のテンプレートファイルをまとめたベースファイルを用意しました。
以下のダウンロードボタンをクリックすると、ベースとなるブランクテーマをZIP形式でダウンロード可能です。
WordPress自作テーマは難しいのか?

「WordPressの自作テーマに挑戦」と想像すると、最初は「難しそう」と感じがちです。
しかしPHPやテンプレート構造の基本を押さえれば、実はハードルはぐっと下がるものです。
一方、サイト規模や要件が増えると、設計やコード量が膨大になりやすいのも事実です。
本節ではその意味について負荷ぼって解説していきたいかと思います。
慣れてしまえば難しくない
結論、最初の壁を超えれば、テンプレート階層や関数の関係性が自然と理解できるようになります。
WordPress公式ドキュメントを参考に、独自関数やファイル処理の流れを覚えてしまえば、あとは自分でいかようにもカスタマイズしていくことが可能です。
また、テンプレートタグやカスタム投稿タイプの使い分け経験を重ねれば、さらに自由度の高いレイアウト構築もお手のものでしょう。
サイト規模によっては難しい
ただし、サイト規模が大きくなるほど、自作テーマの難易度は一気に上がります。
たとえばカスタム投稿タイプを追加する際、個別ページだけでなく投稿一覧(archive)のテンプレートやリライトルールを細かく設定しなければなりません。
カスタムタクソノミーやカスタムフィールドを組み合わせた複雑な絞り込み検索やページネーション処理も発生し、テンプレート階層の理解だけでは対応しきれないケースが増えます。
また、プラグイン依存の要件が不可避となる場合が多く、フォーム送信やキャッシュ管理、多言語対応、EC機能など、WordPress本体だけでは補えない機能を外部プラグインで実装すると、バージョンアップ時に互換性問題が起こりやすくなります。
このように、規模によってはテーマ開発とプラグイン保守を同時に行う必要があり、運用コストやテスト工数が膨大になる可能性があることにに注意しましょう。
WordPress自作テーマを作るメリット

そんなWordPress自作テーマですが、実際に作るメリットはどんなものなのでしょうか。
結論から言えば「自分次第で色々なことができるようになる」というメリットが大きいです。
本節では、メリットを具体的に見ていきたいかと思います。
カスタマイズ性に優れる
WordPress自作テーマ最大のメリットは、あらゆるデザイン・機能要件に応じて自由自在に設計できる点です。
テンプレート階層を活用すれば、投稿・固定ページ・アーカイブなどのレイアウトを個別にカスタマイズ可能です。
functions.phpを編集すれば独自ウィジェットやカスタムメニュー、ショートコードなど多彩な機能を追加でき、CSSやJavaScriptもテーマフォルダ内で一括管理でき、完全独自な実装が可能となります。
こうした柔軟性により、サイトの要件変更や機能追加にも素早く対応でき、長期的な運用コスト削減につながります。
ブランド一貫性を保てる
WordPress自作テーマなら、ブランドガイドラインに沿ったデザインを細部まで再現できます。
自社ブランドの使用しているカラースケールや、戦略的な情報の出し方に至るまで、ほぼ全てが思いのままに実装することが可能です。
既存テーマでは用意されたカラーパレットやフォントに制約があり、微調整に時間がかかったり、そもそも対応できないケースも少なくありません。 独自テーマならCSSカスタムプロパティやSCSS変数で色やタイポグラフィを一元管理。
結果として、一貫性のあるサイトデザインはユーザーの信頼感を高め、ブランド認知の向上にも寄与。ビジネス価値を最大化する自作テーマならではの大きなメリットです。
保守性が高まる可能性
既存テーマでは、数多くの機能やフックがあらかじめ組み込まれているぶん、内部ロジックや独自仕様が見えづらく、アップデート時に思わぬ不具合が発生するリスクがあります。
どこで何が処理されているのか把握できないと、トラブル対応に余計な手間や時間を費やしがちです。
一方、自作テーマならテーマの構造やカスタム機能をゼロから設計するため、ファイル配置や関数の役割、依存関係を事前にドキュメント化できます。
コメントや命名ルールを徹底すれば全体像を理解可能隣となり、モジュール単位でのテストや修正がしやすく、改修時の影響範囲も瞬時に把握できます。
自作テーマであれば、長期的なメンテナンスコストを大幅に削減することも可能でしょう。
ただし、自作がゆえのリスクも十分にあるため、保守性という観点では一長一短と言えるかもしれません。
WordPress自作テーマの作り方

WordPress自作テーマを作るには、まず必要なテンプレートファイルを準備します。
次に、ローカルの仮想環境にWordPressをインストールし、自作テーマを/wp-content/themes/に配置することで運用を開始することができます。
本章では、最も基本的なステップをご紹介したいかと思います。
ベースファイルを用意する
まず/wp-content/themes/配下に任意のフォルダ(例: my-themeなど)を作成し、基本ファイルを揃えます。
- style.css … テーマ名やURI、説明、バージョン、著者情報など
- index.php … 投稿ループやHTMLの土台
- functions.php … 各種ファンクション記述
- header.php、footer.php、sidebar.phpなど共通ファイル処理
このパッケージ処理は、前述のブランクテーマファイルをカスタマイズすると良いでしょう。
仮想環境へインストール
ローカルでの開発を素早く始めるため、仮想環境(Docker、Local by Flywheelなど)を利用すると便利です。
以下の手順を参考に導入してください。
- 仮想環境を用意する
- Docker Composeの場合:プロジェクト直下に
docker-compose.ymlを作成し、公式のWordPressイメージとMySQLコンテナを定義。 - Local by Flywheelの場合:GUIのガイドに従ってWordPressが稼働する環境を簡単に構築できます。
- Docker Composeの場合:プロジェクト直下に
- テーマフォルダを配置
フォルダを仮想環境内のwp-content/themes/ディレクトリにコピー - テーマを有効化
WP管理画面の「外観」→「テーマ」から自作テーマを有効化
まとめ
WordPress自作テーマは、既存テンプレートにはない自由度とブランド統一を実現します。
カスタマイズ性や保守性を高めつつ、サイト規模に応じて難易度を調整できるのも魅力です。
ぜひ本記事を参考に、自分だけのWordPressテーマ制作に挑戦してみましょう。
この記事の著者

児玉慶一
執行役員/ AI・ITエンジニア
愛称: ケーイチ
1999年2月生まれ。大学へ現役進学後数ヶ月で通信キャリアの営業代理店を経験。営業商材をもとに100名規模の学生団体を構築。個人事業主として2018年〜2020年2月まで活動したのち、2020年4月に広告営業事業を営む株式会社TOYを創業。同時期にITの可能性を感じプログラミングを始め、現在はITエンジニアとして活動中。2021年にLeograph株式会社に参画し、AI研究開発やWebアプリ開発などを手掛ける。 「Don't repeat yourself(重複作業をなくそう)」「Garbage in, Garbage out(無意味なデータは、無意味な結果をもたらす)」をモットーにエンジニア業務をこなす。
【得意領域】
業務効率化AIモデル開発
事業課題、戦略工程からシステム開発
Webマーケティング戦略からSaaS開発