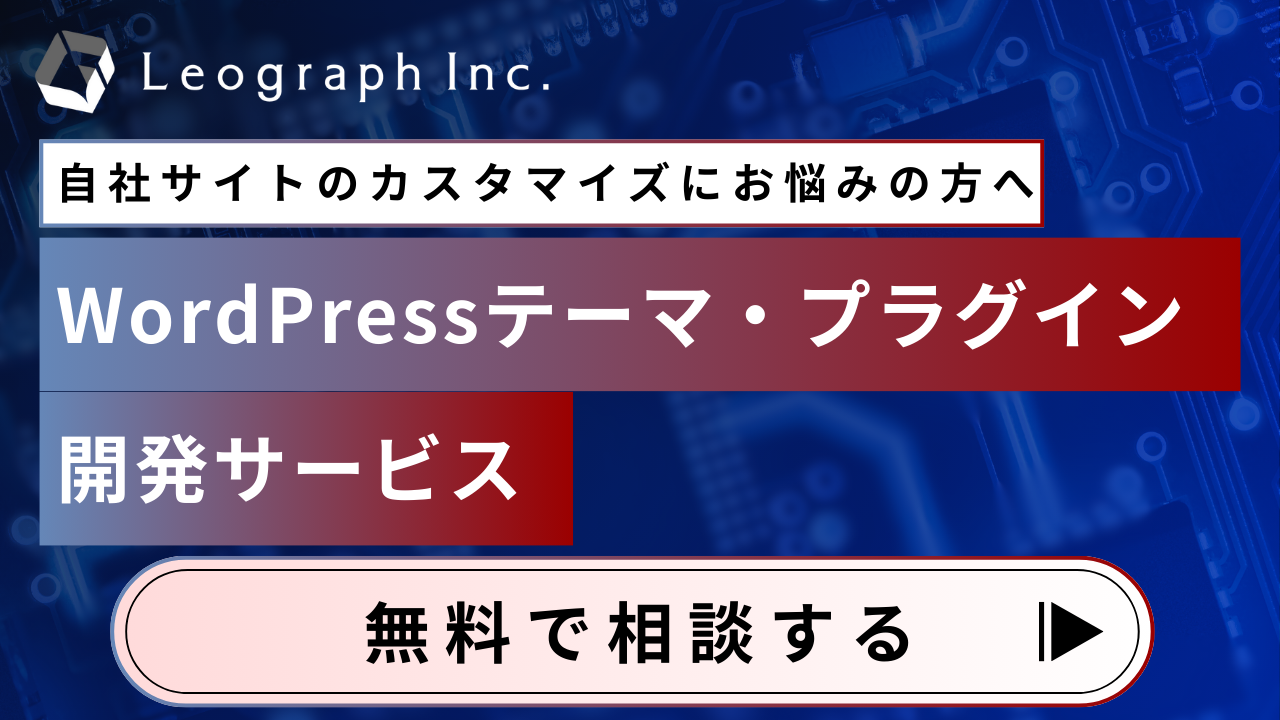WordPressプラグイン開発のメリットとは?開発の難易度やプラグインの構造を解説!
昨今、WordPressを使用したWebサイト運用が主流といっても過言ではない状況で、プラグインの活用はサイト運用の効率性を左右します。
そんな中、「プラグインは自社で作ってもいいのか?」「自社でプラグインを作るメリットはあるのか?」といった疑問が生まれることもあろうかと思います。
本記事では、WordPressプラグインを自作するメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
WordPressプラグインとは?

WordPressプラグインとは、WordPress本体の機能を拡張・カスタマイズするためのパッケージです。
独自・テンプレートテーマだけでは実現しづらい検索機能やフォーム作成、SNS連携など、さまざまなアドオンをプラグインを追加するだけで簡単に導入可能になります。
また、プラグインには「公式ディレクトリで公開するもの」と「自社内やクライアント専用に非公開で運用するもの」があり、それぞれメリット・デメリットが異なるのが特徴です。
公開プラグインと非公開プラグインがある
公開プラグインとは、プラグイン作成者がWordPress公式ディレクトリに登録し、世界中のユーザーが無償または有償版としてダウンロード・評価できるものです。一方、公開プラグインはディレクトリ規約やセキュリティチェックをクリアする必要があり、アップデート時の審査やユーザー対応も発生します。
対する非公開プラグインは、自社サイトやクライアントのみで利用するため外部に公開しない形式です。開発・配布の自由度が高く、企業秘密や特殊要件を内包できます。
非公開プラグインは、公開プラグインに比べて審査不要・更新も柔軟ですが、利用範囲が限定されるため新規顧客獲得へのアピールをしたい場合には難しくなります。
WordPressプラグインを自作するメリット
そんなWordPressプラグインですが、自作することでサイト運営に多くのメリットが得られます。
既存プラグインでは実現が難しい独自機能を自在に追加できたり、UI/UXの最適化も可能です。
さらに、自作プラグインは自社ノウハウとして資産化できるといっても過言ではありません。
本節では、これらのメリットを「サイトを自由にカスタマイズができる」「フロントビジネスになりうる」という視点で具体的に解説していきます。
サイトを自由にカスタマイズができる
自作プラグインの大きな魅力は、サイトの細部まで自由にカスタマイズできることです。
既存のテーマや汎用プラグインでは実現しにくいデザイン調整や独自機能を思いのままに開発可能になります。
- レイアウトの独自設計
- カスタム投稿タイプの作成
- 独自ショートコード・ウィジェット追加
- 外部API連携による動的コンテンツ埋め込み
- コードの最小化
プラグインの自作はサイト運営の自由度を最大化し、競合との差別化を図る強力な武器となるでしょう。
フロントビジネスになりうる
自作プラグインは単なる機能追加にとどまらず、収益源としても活用できます。
| 販売チャネル | 収益モデル |
|---|---|
| WordPress公式ディレクトリ/自社サイト | フリーミアム+追加機能有料販売 |
| 保守更新プラン | サブスクリプション型 |
| プラグイン提供 | 受託開発相談増 |
| 技術ブログ・セミナー | 情報発信 |
WordPressプラグインを流布した後、カスタマイズや導入支援のオプションを組み合わせ、開発以外の付帯サービスで利益を上乗せするのも有効です。
オープンソースコミュニティと連携して信頼を獲得しつつ、自社ブランドのプラグインとして独自性を打ち出すといった、プラグインを起点としたブランディング施策も取ることができます。
しかし、必ずしもプラグインを公開してやることがメリットだらけではないので、ここからはデメリットに関しても解説していきたいかと思います。
WordPressプラグインを自作するデメリット
WordPressプラグインを自作すると、既存のプラグインでは実現できない独自機能を柔軟に組み込める一方、開発後の運用やサポートはすべて自社の責任となります。
セキュリティ対策やWordPress本体のバージョンアップ対応、バグ修正などの保守業務に加え、問い合わせ対応やトラブルシューティングといった顧客サポートの負担も無視できません。
本節では、自作プラグイン開発に伴うデメリットとして、特に「保守・運用を自社で行わなければいけないこと」「顧客対応の必要性」という2つのポイントにフォーカスして解説します。
保守・運用を自社で行わなければいけない
自社でプラグインを保守・運用する場合、リリース後のすべてのタスクは自社担当になります。
WordPress本体やPHPのバージョンアップに合わせた動作確認や、他プラグインとの互換性チェック、定期的な脆弱性対策の実施は必須です。 バグ発生時には迅速な修正対応が求められ、開発者リソースが圧迫される可能性も高いでしょう。
自社内に技術ノウハウと継続的なメンテナンス体制を構築できない場合、問題発生時の対応遅延が事業リスクにつながる点も押さえておきましょう。
また、アップデートや脆弱性パッチの情報収集も自社で行う必要があり、情報収集コストも意外と見逃せません。
顧客対応の必要の可能性がある
プラグインに有料機能を追加した場合、利用者からの質問やトラブル報告に対応する必要があります。
動作不具合の調査やバージョンアップ時の互換性確認、導入手順の案内など、メールやチャットでの問い合わせが発生しがちです。
対応品質が低いと評価が下がり、ブランドイメージにも影響を及ぼします。
専任スタッフやサポートマニュアルの整備、FAQの公開、チケットシステム導入など、体制構築も重要です。想定以上にリソースを消費する点は事前に把握しておきましょう。
WordPressプラグイン開発は難しいのか?
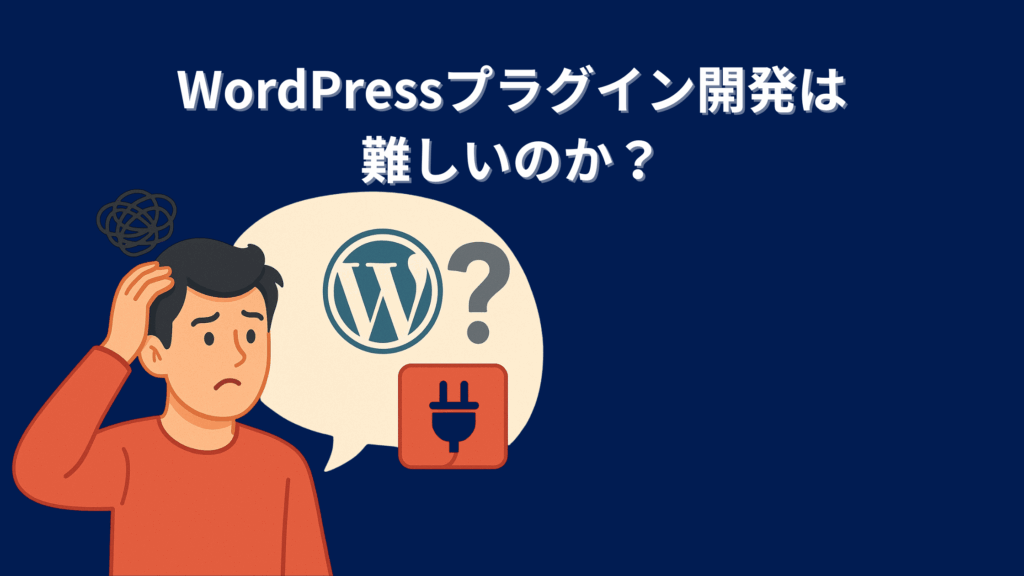
WordPressプラグイン開発の難易度は、目的や必要な機能の規模によって変わりますが、意外と難しくはありません。
基本的にはPHPの知識とWordPressのアクション・フィルターフック、データベース操作に慣れていれば、シンプルなプラグインなら比較的スムーズに作成可能です。公式ドキュメントやコードサンプルも豊富に用意されています。
ただ、前項でも申し上げたような「開発の上流にある要件」との兼ね合いもあり、実現したい規模によって開発の難易度も変わってくると言えます。
WordPressプラグインの構造とは?
WordPressプラグインは、フォルダ内に機能ごとに分けられた複数のファイルやディレクトリで成り立っています。
- コアロジックを担うファイル
- includes/など
- 管理画面のUIを構築するファイル
- admin/など
- CSSやJavaScriptといった静的リソース
- assets/など
以下では、これら4つのメイン要素を順に見ていき、どのようなファイル構成や命名規則を採用すれば実践的かつ効率的にプラグイン開発を進められるかを解説していきます。
コアロジックファイル
コアロジックファイルは、プラグインの機能を実装する中核的なPHPファイルです。
一般的にはxxx-plugin.phpやclass-xxx-core.phpといった名称でプラグインフォルダ直下に配置し、プラグインヘッダーや初期化処理を記述します。
管理画面UIファイル
管理画面UIファイルは、プラグインの設定画面やダッシュボード上の操作画面を実装するパートです。
通常は /admin フォルダ内に ui.php や class-xxx-admin.php として配置し、以下のポイントを押さえましょう。
- add_action()でメニュー・サブメニューを登録
- register_setting/add_settings_section/add_settings_fieldなどによる設定登録
- HTML、URLエスケープを徹底
静的ファイル
静的ファイルは、はプラグインで使用するCSS、JavaScript、画像などのリソースを格納します。
/assetsや/public内にcss/, js/, img/といったフォルダ構成で整理し、wp_enqueue_style/wp_enqueue_scriptで読み込み。(共通要素に読み込ませる関数)
ハンドル名にはプラグイン固有のプレフィックスを付与し、依存関係(deps)やバージョン(ver)を指定してキャッシュ対策を徹底しましょう。
まとめ
WordPressプラグインを自作すると、サイトの機能やデザインを自由に拡張でき、公開すればビジネスチャンスにもなります。
しかし、必ずしも良い面だけではないです。
メリット・デメリットを理解し、運用していくことが肝要でしょう。
この記事の著者

児玉慶一
執行役員/ AI・ITエンジニア
愛称: ケーイチ
1999年2月生まれ。大学へ現役進学後数ヶ月で通信キャリアの営業代理店を経験。営業商材をもとに100名規模の学生団体を構築。個人事業主として2018年〜2020年2月まで活動したのち、2020年4月に広告営業事業を営む株式会社TOYを創業。同時期にITの可能性を感じプログラミングを始め、現在はITエンジニアとして活動中。2021年にLeograph株式会社に参画し、AI研究開発やWebアプリ開発などを手掛ける。 「Don't repeat yourself(重複作業をなくそう)」「Garbage in, Garbage out(無意味なデータは、無意味な結果をもたらす)」をモットーにエンジニア業務をこなす。
【得意領域】
業務効率化AIモデル開発
事業課題、戦略工程からシステム開発
Webマーケティング戦略からSaaS開発