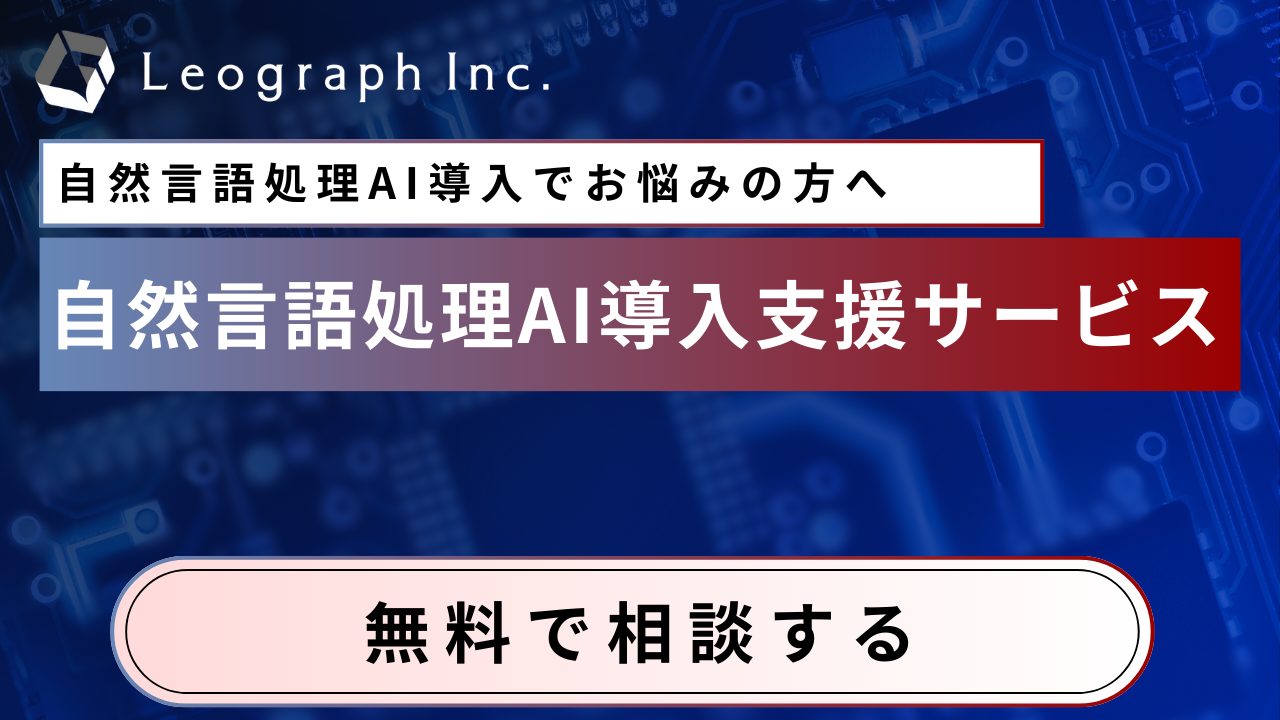生成AIを活用するメリットとデメリットを企業規模ごとに解説!大手導入事例も紹介
近年の生成AI技術の進化に伴い、一部の企業はビジネスプロセスの効率化を主な目的として導入を進めています。
しかし、まだまだ「生成AIは普及した」と言い切るには十分な活用事例があるとは言えません。その裏には「果たして生成AIを使うべきか」「使ったらどんなメリットがあるのか」といった疑念を抱く企業担当者の声があるのです。
そこで本記事では、企業規模ごとに生成AI活用のメリットとデメリットを詳細に解説し、事例も加えてご紹介していくことで、読者の皆様が生成AIの活用の第一歩を踏みやすくなるようにしていければと思います。
なぜ生成AIが注目されているのか
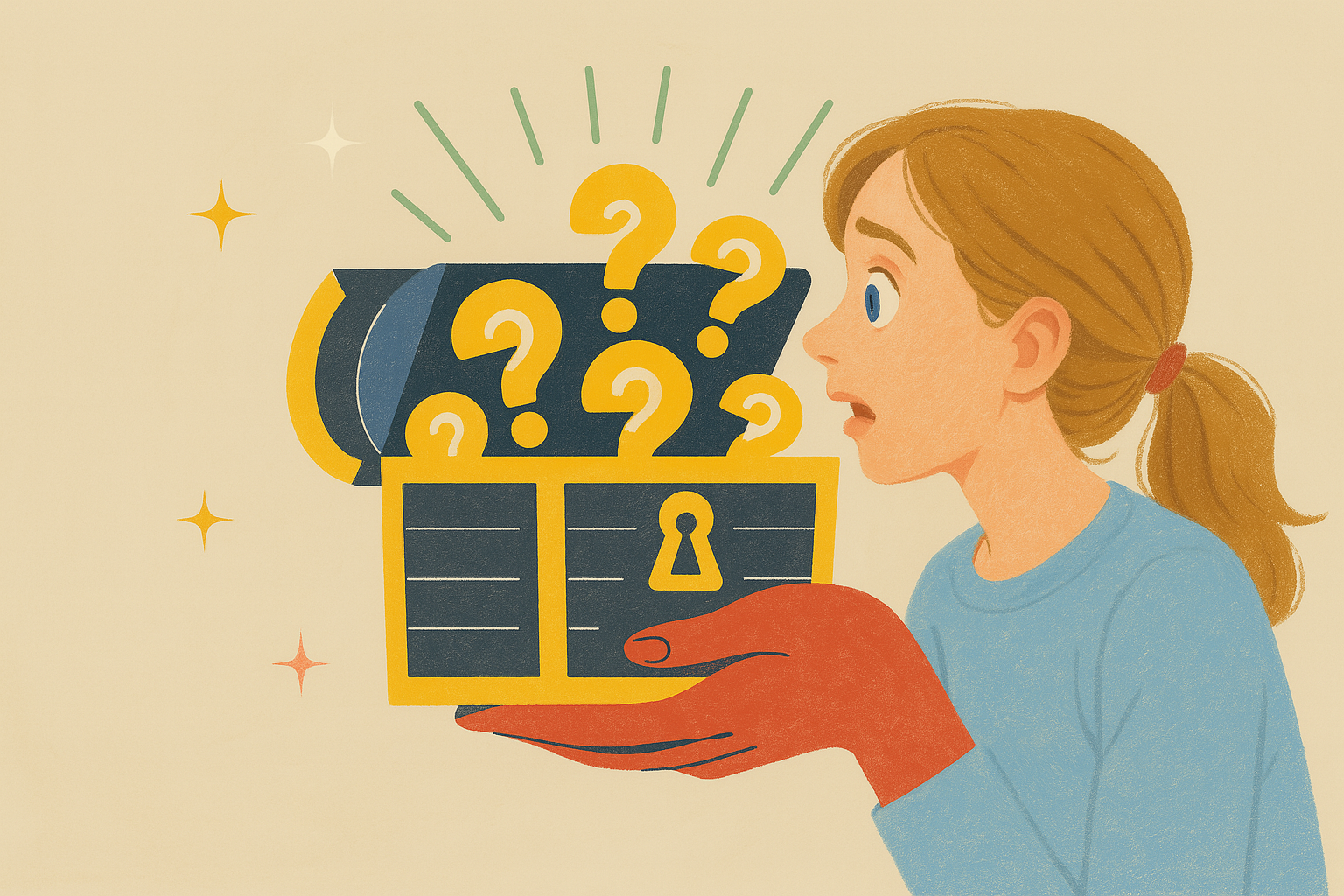
生成AIを一度でも触ったことのある方の中でも、「なぜこんなにもビジネスシーンで生成AIが注目されているのか」について明確に言える人はどのくらいいるのでしょうか。
もちろんそこにはれっきとした根拠があります。
本節では生成AIが注目される理由について大きく分けて3つご紹介します。
新規事業を立ち上げやすくなる
現代の生成AIは非常にハイクオリティな成果物を提供してくれます。それに加え、新たなアイデアの創出にも役立てる事が可能です。
これにより、新規事業の立ち上げが従来よりも格段に容易になります。
主にスタートアップ規模の企業が抱える課題として、事業創出のためのPoC段階でリソースをうまく活用できないといった“キャッシュ・ノウハウ”要因のものがあります。
そこに、従来であれば豊富な資金力と優秀な人材の採用が要される部分を生成AIが代替してくれるため、体力の少ない企業組織でも新規事業を立ち上げるハードルが下がるのです。
人材不足の解消につながる
生成AIはもはや「ホワイトカラー人材以上の能力を持っている」と言われています。
このことから、生成AIの活用により人材不足の解消が期待されるのです。
近年、少子高齢化の煽りを受け、地方中小企業を筆頭に働き手の確保は困難を極めています。実際、正社員の人手不足を感じている企業は全体の過半数を超え、コロナ禍以降では過去最高に達しているという統計も存在するほど。(帝国データバンクの人手不足に対する企業の動向調査(2025年1月)より)
この課題に真っ向から解決をしてくれるのが生成AIの導入です。
生成AIは「書く」「聞く」「解釈する」「まとめる」「分析する」などのこれまで人間が担当してきた業務を遂行してくれるため、人材が足りないとあえぐ企業にとって手を伸ばさないわけにはいかないでしょう。
事業経費の削減ができる
また、生成AIは月額サブスクリプションのWebアプリケーションであることがほとんどで、その金額帯は「数ドル〜十数ドル」です。日本円にしておよそ数千円から数十万円、一般的にはビジネスプランでも数万円での利用が可能です。
この費用でありながらもなせる技は人一人以上という魅力的な費用対効果が注目され、企業経営視点では「事業経費の削減」ができるという事実があります。
考えてみれば、給与+社会保険料+税金+諸経費を合わせた人件費と比較した時、同じ成果物を期待するのであれば生成AIを使った方が圧倒的に有利になるのです。
これには多少の論争が巻き起こりますが、そうはいっても営利企業にとっては優先事項は利益の創出であり、そのためのコストカットはインパクトが大きければ大きいほど避けれれぬものでしょう。
最近では生成AI導入による大手企業の大量解雇がニュースに出てくるようになりましたね。
生成AIを活用するメリット
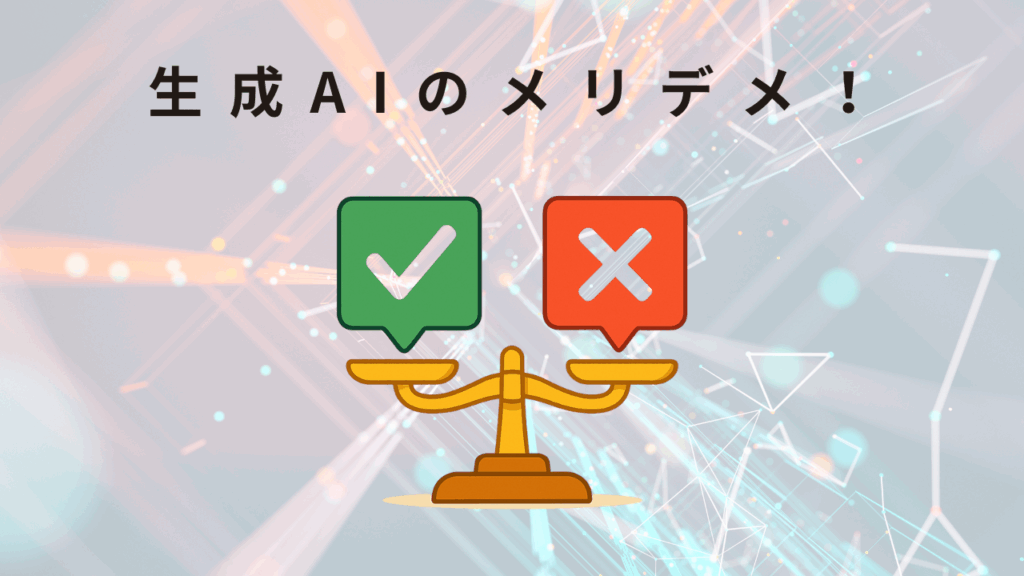
ここまでご紹介した生成AIが注目される理由から紐解いていくと、導入を検討している企業担当者さんにとっては「具体的にどんなメリットがあるのか?」が気になってくるかと思います。
メリットと言っても、企業規模によって享受できるものが少し変わってきますので、本節では“企業規模ごと”に生成AIを活用するメリットをご紹介していきたいと思います。
スタートアップが生成AIを活用するメリット
スタートアップにとって、生成AIの活用は成長促進に大きなメリットをもたらします。組織の限られたリソースを効率的に活用し、業務プロセスの自動化や最適化を実現してくれるでしょう。
というのも、スタートアップは巨額資金調達でもしない限り、キャッシュがショートするリスクと戦い続けるレベルには体力がないことがほとんど。
そこに、キャッシュが少ない中でも比較的手を出しやすい生成AIは、費用対効果が抜群です。
中小企業が生成AIを活用するメリット
中小企業にとっての生成AI活用のメリットは、なんと言っても業務効率化です。中小企業は組織力強化と事業促進のバランスに挟まれた苦しい思いをしているところが多い印象を受けます。
そんな課題を持つ中小企業にとっては、生成AIは日常業務の自動化を促進し、従業員がコア業務に集中できる環境を整える事ができます。
時間とコストの削減が目に見えて実現できるため、それまで部門間で兼業していた人材も本来の業務にリソースを集中させる事ができるのです。
また、生成AIの持つデータ分析機能を活用することで、戦略的な意思決定をスピード感を持って行う事ができるようになります。
大企業が生成AIを活用するメリット
大企業にとっての生成AI活用のメリットは、競争優位性の確立につながる事です。
これは必ずしもポジティブな話題ではないのですが、生成AIサービスの普及は導入のハードルが低いにも関わらずハイパフォーマンスを出す事ができるイノベーションです。裏を返して言えば、「生成AIを使わないと市場から取り残されるリスクが高まる」ということになります。
既に一部の大手企業は生成AIの導入に積極的ではあるものの、まだまだ普及しているとも言い切れず、まだ導入をしていない大手企業は決断に迫られていることでしょう。
生成AIを活用するデメリット
さて、生成AIの導入には多大なメリットがありますが、もちろん、一方では企業にとって様々なデメリットも存在します。
こちらも企業規模によってデメリットになる部分が違うため、本節ではスタートアップから大企業までのそれぞれにおける生成AI活用のデメリットについて詳述します。
スタートアップが生成AIを活用するデメリット
スタートアップにとって、生成AIの活用は必ずしもメリットで溢れているわけではありません。
生成AIは簡易的にハイクオリティな成果物を作る事ができるものの、その成果物を左右するのは、生成AIを扱う人間のリテラシーに大きく左右されます。
また、そもそもリソースの自由度が低いスタートアップにとって、いくら安価な生成AIだからと言って無駄な投資をするわけにもいきません。
もし導入した生成AIを上手に活用できずにいたら、宝の持ち腐れと言わざるを得ないでしょう。
中小企業が生成AIを活用するデメリット
中小企業が生成AIを活用する際にもデメリットがあります。
とりわけ、ITリテラシーの低いベテラン中小企業は、長年ITに関するナレッジを社内で温めずに生き残ってきた可能性が高いです。また、良くも悪くも属人的な組織で会社がうまく回ってしまっているパターンも少なくありません。
そんな中、世間で話題になっている生成AIをいち早く導入しようとしても、現場レベルでは受け入れられず、アレルギー反応を起こす危険性があります。
これは生成AIに限った話ではなく、中小企業の体質に合わないシステム導入の失敗はよくある話です。
大企業が生成AIを活用するデメリット
大企業、中でも株式市場に上場している企業には、生成AI活用のデメリットが大きいと言えます。(スタートアップ、中小企業と比較して)
まず、大企業はステークホルダーの数がとても多く、下手なシステム運用はできないという“制約”が存在します。特に上場企業は株主の母数が多いため、ROIを意識した生成AIの活用を検討しなければなりません。
また、コーポレートガバナンスも重要視されるため、データセキュリティやプライバシー保護の観点から、大企業にとってはコンプライアンス対応がより一層複雑化します。
生成AIの活用のためにも、組織全体での理解と協力が不可欠です。
大手企業の生成AI導入事例
では、ここで企業担当者向けに大手企業の生成AI導入事例を3つご紹介します。
もし皆様の会社で生成AIが未導入であるなら、下記の事例は「今後社内で起きうる事例である」と考えておくといいでしょう。
マイクロソフトの人件費削減
マイクロソフトは生成AIの導入を通じて、人件費の削減に成功しています。
AIを活用した自動化ツールを導入することで、ルーティン業務やデータ分析作業の効率化を図りました。これにより、従業員はより高度な業務や創造的なタスクに集中できるようになり、全体的な生産性が向上しました。
しかし、これは同時に「必要な人員数を絞る事ができるようになった」とも言い換えることができ、結果的に大量解雇へとつながることとなったのです。
現地のニュースでも話題となったマイクロソフトの大量解雇については、下記のニュース記事をご覧ください。(ブルームバーグのマイクロソフトの米大規模人員削減に関するニュース記事)
ソニーの生産性向上
2025年6月にAWSサミットで発表された内容によれば、ソニーグループは生成AIの導入により「毎月5万時間の労働時間を削減」しており、既に数百件に上るビジネスでのPoCに成功しています。
その背景には、生成AIプラットフォームをAWS環境で構築した「Enterprise LLM」と、「プレイグラウンド」と呼ばれるテスト環境の独自構築があります。
これにより、少なくとも40件のビジネスは本番検証が済んでいるとのことです。
LINEヤフーの生成AI導入義務化
LINEヤフーは、2025年7月14日に全従業員およそ11,000人を対象に、生成AIの業務活用を義務化するという、極めて先進的な働き方のモデルを本格導入しました。
これは単なるツールの利用推奨にとどまらず、企業文化そのものを塗り替える意思表明とも取れるムーブメントでしょう。
この方針により、すべての業務におけるAIの積極的な導入を徹底し、生成AIの活用比率を実質100%へと高めることで、今後3年間で業務の生産性を従来比で2倍に引き上げるという明確な目標を掲げています。
もはや「生成AIを使えるかどうか」は問題ではなく、「どのように使いこなし、組織に変革をもたらすか」が問われる時代ということなのでしょうか。
まとめ
今や生成AIを知らない人の方が珍しい気もしてくるこの時代。
企業活動では盛んに行われる業務最適化と資本効率の最適化、その中で生成AIが吉と出るか凶と出るか。
それは、生成AIについてのリテラシーをいかに高めるかに左右されるのは明白です。
この記事の著者

児玉慶一
執行役員/ AI・ITエンジニア
愛称: ケーイチ
1999年2月生まれ。大学へ現役進学後数ヶ月で通信キャリアの営業代理店を経験。営業商材をもとに100名規模の学生団体を構築。個人事業主として2018年〜2020年2月まで活動したのち、2020年4月に広告営業事業を営む株式会社TOYを創業。同時期にITの可能性を感じプログラミングを始め、現在はITエンジニアとして活動中。2021年にLeograph株式会社に参画し、AI研究開発やWebアプリ開発などを手掛ける。 「Don't repeat yourself(重複作業をなくそう)」「Garbage in, Garbage out(無意味なデータは、無意味な結果をもたらす)」をモットーにエンジニア業務をこなす。
【得意領域】
業務効率化AIモデル開発
事業課題、戦略工程からシステム開発
Webマーケティング戦略からSaaS開発