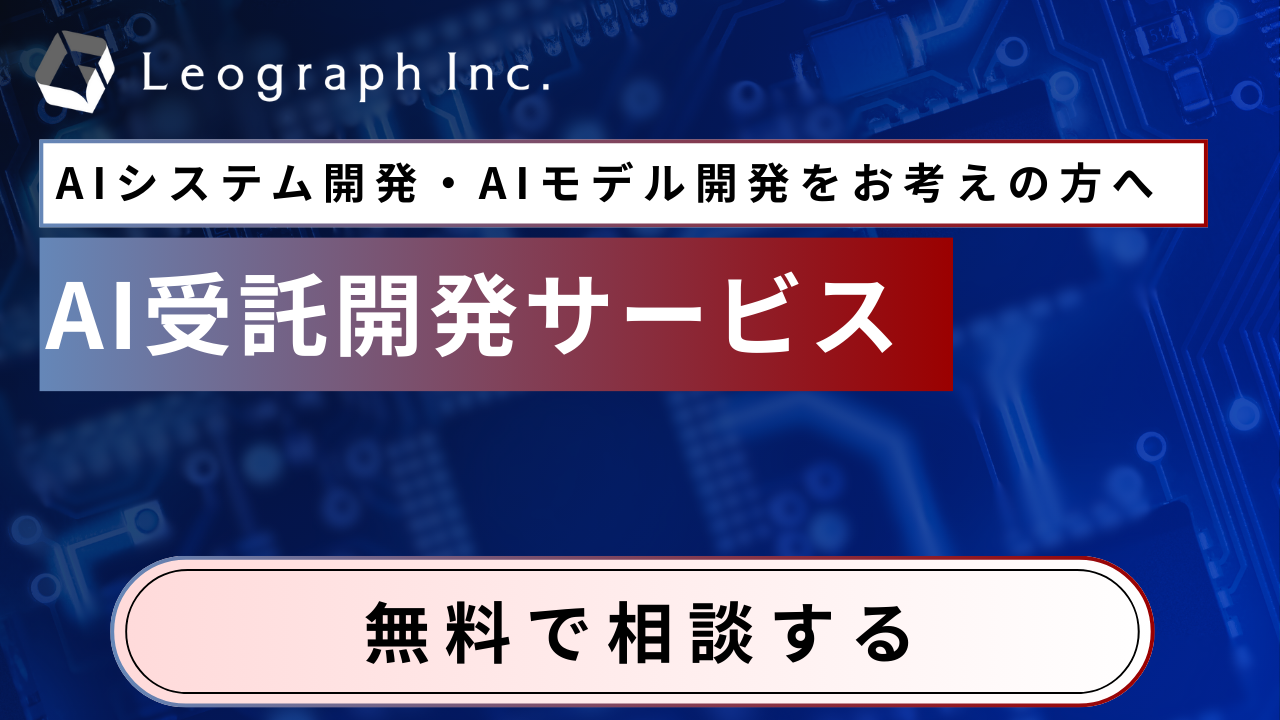AI(人工知能)とは?種類や活用事例などをどこよりもわかりやすく解説!
世はまさにAI時代。さまざまな業種・業態において、古今東西AIを活用し始めています。
この記事に辿り着いた方も、ひょっとしたら社内でのAI活用についての議論の最中かもしれませんし、少なくともAIについて「知りたい」と思いでしょう。
本記事では、人工知能(AI)の基本概念や種類を明確に解説し、予測、画像認識、感情分析などAIの多岐にわたる機能について詳述します。
さらに、製造業からカスタマーサポートまでの具体的な活用事例を5つ紹介し、AI導入に必要なデータや技術についても触れます。
AIの全体像をどこよりもわかりやすく理解するための内容となっています。
AIとは
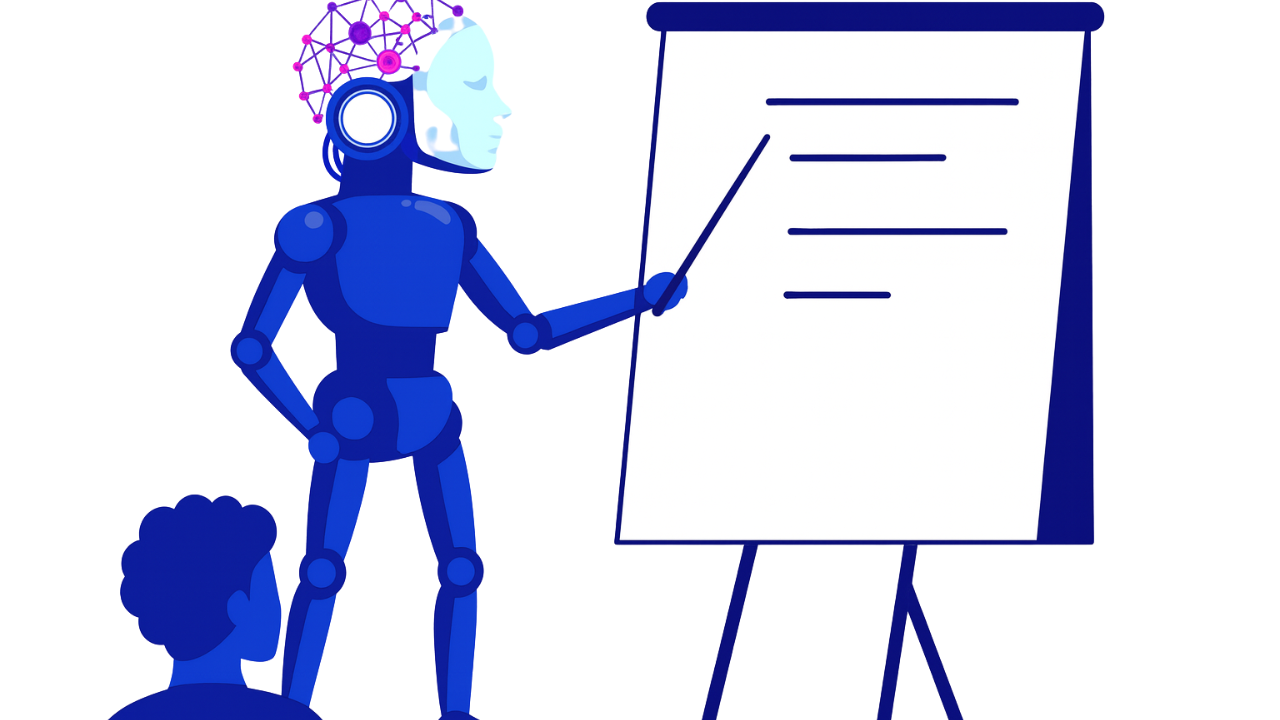
前提として、そもそもAIとは何のことを指すのかを整理しておきましょう。
人工知能(AI)とは、コンピュータやシステムが 人間の知能機能を模倣し、学習、推論、 問題解決を行う技術の総称です。
つまり「AIとは〇〇である」といった、特定のものを指すことではなく、概念そのものを指しているのです。
AIの定義
実は、AIの定義とは“明確なもの”が決まってはいません。
厚生労働省が発表している資料によれば、「人工知能(AI:artificial intelligence)については、明確な定義は存在しないが、大量の知識データに対して、高度な推論を的確に行うことを目指したものとされている。」とあります。(参考: 厚生労働省の「AIの定義と開発経緯」)
つまり、AIは広範かつ多岐にわたるということです。
機械学習との違い
よく聞かれる質問の一つに「AIと機械学習はどう違うの?」と言うものがあります。
機械学習(Machine Learning)は、人工知能(AI)の一分野として位置付けられます。
AIを“目指すべき最終ゴール・概念”とするのであれば、機械学習は“そのゴールを達成する代表的な手段”のことを指します。
生成AIとの違い
また、最近はChatGPTなどのサービスを代表とする生成系AIが話題にあがります。一部では生成系AIのことをAIと呼称する方もおられますが、これは定義的には少し違います。
生成系AIとは、人工知能という大きな目標を達成するための手段として位置付けられ、上位概念には「ディープラーニング」というものがあります。
ここまでのお話をテキストだけでは理解しづらい部分があると思いますので、以下に概念図をまとめてみました。
とは?-1024x576.png)
AIができること
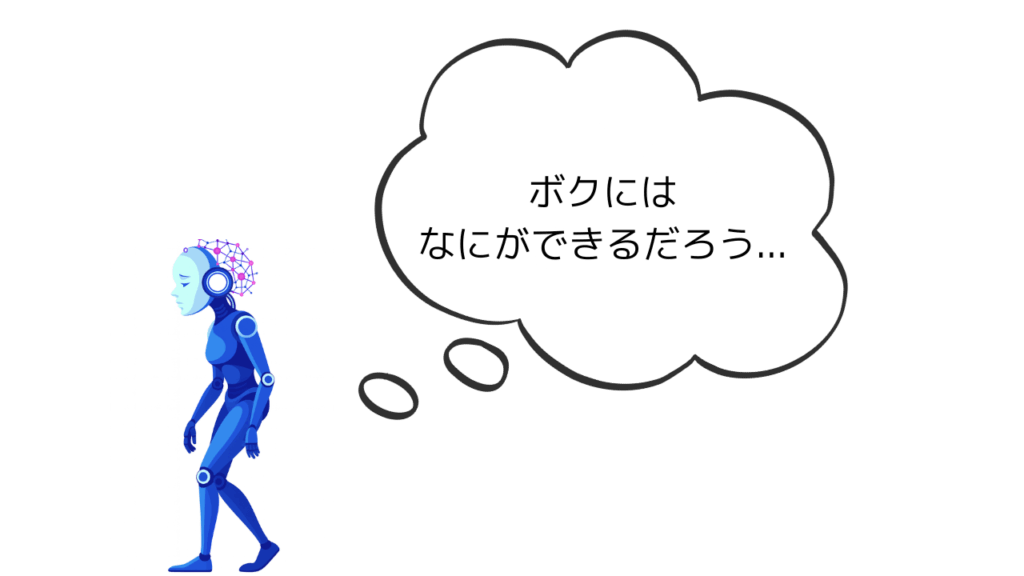
AIは現代社会において多岐にわたる分野で活用され、その能力は日々進化しています。
ただし、AIの特性によってできること(得意なこと)が変わってきますので、AIであれば何でもいいというわけではありません。
本節ではAIの大枠での“できること一覧”をご紹介します。
数値の予測
数値の予測は、AIが特定のデータセットに基づいて将来の数値を予測する能力を指します。
主に時系列分析や回帰モデルを用いて行われ、用途としては販売予測、株価の動向予測、需要予測などがあります。
AIは、過去のデータからパターンやトレンドを学習し高精度な予測を実現してくれるため、企業にとっては在庫管理の最適化やリスクの低減、戦略的な意思決定を支援することが可能となります。
最近では分析アルゴリズムも充実してきており、多様なニーズに柔軟に対応することができるようになりました。
画像の識別
画像の識別は、AIが視覚データを解析し、対象物やパターンを特定する技術です。また、画像分類という名称で呼ばれる分野もこれにあたります。
畳み込みニューラルネットワーク(CNN)などの深層学習アルゴリズムを用いて実現されるこの分野は、大量の画像データを学習することで、物体認識、顔認識、医療画像診断、自動運転の環境認識など、多岐にわたる分野で活用されています。
例えば、医療分野ではX線画像を解析して早期の疾患発見を支援したり、製造業では不良品の自動検出に貢献して労働生産性をあげたりなど、この技術もまた多くの分野でバリューを出しています。
感情の分析
感情の分析は、AIがテキスト、音声、画像などのデータから人間の感情や心理状態を識別・評価する技術です。自然言語処理(NLP)や機械学習アルゴリズムを用いて実現されます。
例えば、SNSの投稿を解析し、ポジティブ・ネガティブな感情傾向を把握することができます。実際に、一部の企業は顧客満足度の向上やマーケティング戦略の最適化に活用しています。
また、コールセンターでは顧客の声のトーンを分析し、対応の改善やスタッフのトレーニングに役立てられています。
AI感情分析の精度向上により、より細やかな人間理解と高度なサービス提供が可能となっていくでしょう。
参考:SNS広告の最新トレンドとは?ショート動画広告、AI活用、各媒体の特徴など徹底解説 | CYANd Inc.
AIの活用事例5選
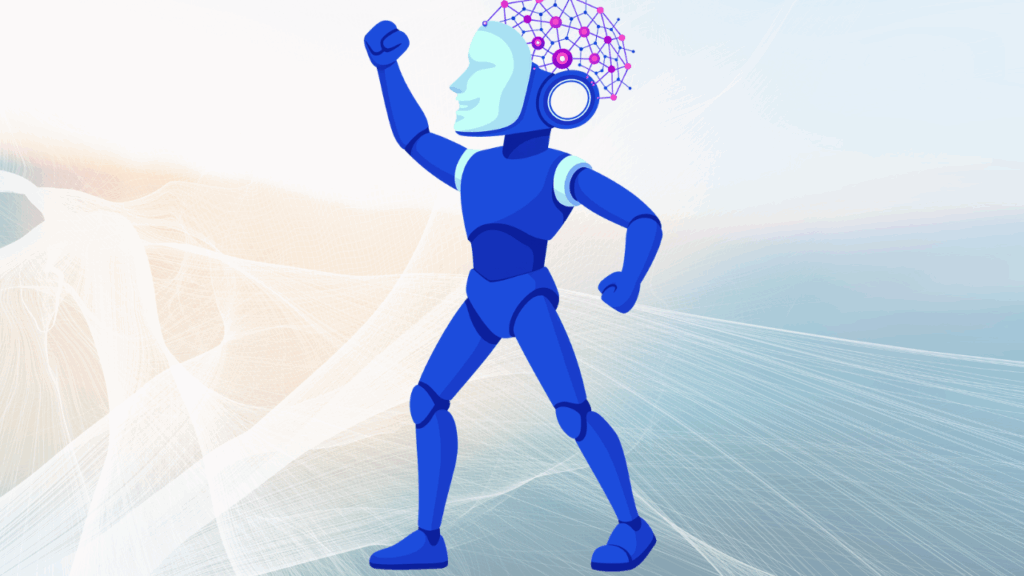
さて、AIにできることが多岐にわたることは自明なことですが、実際にどのように活用されているかについてはそこまで知られていない印象を受けます。
そこで本節では、人工知能が実際に活用されている具体的な事例を5つ厳選してご紹介します。
生産現場での画像認識

画像認識AI技術は、端的に言えば「人間の目視による判別」を自動化できるため、その場に人間がいる必要性が薄まります。言い換えれば、人間がやらなくてもいい業務範囲が増えてきたのです。
一見、人の仕事を奪ってるように聞こえますが、この人材不足・少子化の時代にそんなことは言っていられません。
本来人間がおこなってきた目視による確認ですが、これを代替した具体事例としては「JR西日本のレール傷管理業務へのAI活用」です。
京都のHACARUS社との共同開発により、JR西日本はAIを活用したレール探傷車エコー画像の自動判定システムの開発に共同で着手をし始めたと発表されました。
これが本格運用されれば、これまで人的リソースに依存し切っていた目視による確認作業を大幅に削減することが予想されます。
製造業での需要予測

製造業において、経営リスクに直結してしまうのが「在庫管理の失敗」です。多くの場合はシーズン前段階でロットで原材料を仕入れる必要がありますが、もし仮に市況の変化に対応せず仕入れ最適化を怠れば、仕入れ原価がそのまま負債に回ってしまいます。
そこで、製造業では需要予測AIが注目され始めています。
AI技術を使うと、過去の販売データや市場動向、季節変動など多様なデータを統合的に分析することで、将来の需要を正確に予測することが可能となります。これにより、在庫管理の最適化が可能となり、過剰在庫や欠品といったリスクを低減します。
具体的事例で言えば、2023年時点でキリンビールがブレインパッド社との共同開発により「製造計画作成アプリ」を運用し始め、人的リソースの大幅な削減を実現しています。このように、大手企業から順番に需要予測AIの導入が顕在化し始めており、この流れは次第に社会全体へ浸透していくと見ていいでしょう。
広告運用での最適化
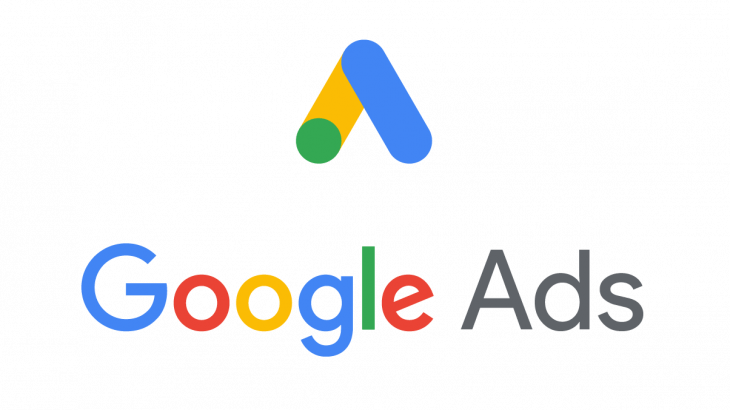
マーケティングプロセスの重要項目の一つである「広告運用」。これも数値分析をメインとして、さまざまな環境要因をチェックしつつ、適宜予算配分などをしていかなければいけない大変な業務です。
この業務も、実はAIが最適化してくれます。
例えばGoogle広告のP-MAX広告では、運用者側は最初の設定をするだけで、「基本的に放置プレイ」でコンバージョンに向けて広告を最適化してくれます。
これは、Googleの膨大なトラッキングデータやCookie処理により、Google検索を利用するユーザー(YouTubeも含む)のペルソナをAI予測し、適切なタイミングで適切な広告を出稿してくれることに起因します。
SNSの口コミ分析

SNSの口コミは、顧客ターゲットの声をリアルに反映している重要な一次情報です。また、業種により異なりますが、SNSでマーケティングを成功させるためには、UGC(User-Generated Content)と呼ばれる「SNSユーザーが作ってくれた自社に関するコンテンツ」の上手な活用が求められます。
ここでキーマンとなるのが「口コミ分析AI」です。無数に情報が泳いでいるSNSの中で、自社にとって有効なデータを集めてくれるAIのことを指します。
具体的には、AnyMind Group社の「AnyTag」というWebアプリケーションが今年に発表したAnyTag Insightでは、ブランドに対する生活者の感情や思考、行動動機を可視化するAI活用機能が搭載されています。
このサービスは多くの大手企業にも採用されており、非常に信頼度の高いAI系サービスと言ってもいいでしょう。
カスタマーサポートのチャットbot導入

最後の活用事例は「カスタマーサポート系業務のAI活用」に関する事例です。この業務も、たとえ多くがテンプレート作業であったとしても、人間が行うには退屈かつ苦痛である場面が多いのです。
また、企業にとっても教育管理体制をしっかりしておかなければならず、諸コストがかさんでしまいます。
そこで、最近は生成AIを利用したチャットbotを導入している企業がかなり増えてきました。しかも、一からチャットbotを開発するよりも便利な「ノーコードでチャットbot構築できるWebサービス」などが台頭してきました。
有名な事例では、「チャットプラス」というものがあります。このサービスでは、月額たったの1,500円でチャットbotを社内業務に構築することができ、通常人間が行う業務の大幅な負担削減に貢献しています。
AIを作るためには

ここまでAI活用が盛んになってくると、次第に担当者さんや経営者達はこのように思い始めるのではないでしょうか?
「弊社でもAIを作り、何かしたい」
しかし、AIを作るというのは、目的の大小によりますが大変な工数を踏む必要があるのをご存知でしょうか。もし少しでもAI開発に興味があるという方は、ぜひ本節での開発工程を参考にしていただきたいと思います。
また、AI開発の費用相場感については以前筆者が解説した記事が参考になりますので、適宜そちらもご覧ください。(参考: “Leograph Media Forum – AI開発のコストが高い理由とは?費用相場や代表的事例も解説”)
大量のデータの用意
AIの開発には、大前提として大量かつ多様なデータの収集が不可欠です。データは、公開データセットや自社で生成されたもの、外部から購入したものなど、さまざまなソースから取得されます。
収集したデータは、品質を確保するために前処理が必要であり、ノイズの除去や欠損値の補完、正規化などの工程を経ます。また、データのラベリング(AIにデータの正解を教えるためのラベル付け)も重要な作業であり、正確なタグ付けがAIモデルの精度向上に直結します。
しかし、データの用意は単純作業ではなく非常にスキルとセンスの求められる作業なのです。
集めるデータが本当に自社の目指すAIに貢献するものなのか、データの質はしっかり担保されているのか、それらを見極める能力が求められます。
サーバー費用の確保
AIの開発および運用には、膨大な計算資源(コンピューティングリソース)が必要になります。これに伴い、サーバー費用の確保はプロジェクト達成のための絶対事項です。
単的に、AIの開発には「想定よりも膨大な予算」が必要になると考えてください。
まず、クラウドサービスとオンプレミスの選択肢を比較検討することになりますが、多くの場合はAWSやAzureといったクラウドサービスを使うことになるでしょう。
クラウドサービスは初期投資が抑えられつつも柔軟なスケーリングが可能ですが、長期的なコストを考慮する必要があります。
また、予算の適切な配分を行うためには、プロジェクトの規模や必要な計算資源を正確に見積もることが求められます。これには、モデルの複雑さやデータ量、運用期間などを考慮した詳細なコスト分析が必要です。
Webアプリケーションをデプロイするときとはまた一風違ったインフラ構成が求められるので、サーバー費用の計算にはAIに特化した設計が必要となりますので、注意が必要です。
AIエンジニアの採用
AI開発をするエンジニアの仕事は従来のシステムエンジニアリングとは違い、AIに関する専門知識が幅広く求められる領域です。
機械学習や深層学習に関する専門知識を持ち、PythonやRなどのプログラミング言語に精通した人材を求めることが必要です。加えて、ビッグデータの処理能力や統計解析のスキル、さらには問題解決能力も重視されます。
こういったAIエンジニアは現在の日本の労働市場では稀な存在で、優秀な人物を採用しようとすればかなりの採用コスト・人件費を支払うことになると覚悟しておいた方がいいでしょう。
まとめ
AIを導入したい、AIを活用したいという声が大きくなることに比例して、それに関連する情報も多くなった昨今ですが、だからこそ適切に情報を処理することが必要です。
この記事だけでなく、AIに関する知識を取り入れる際は見極める力を持っていただきたい、そう思い筆者の言葉とさせていただきます。
お読みいただきありがとうございました。
この記事の著者

児玉慶一
執行役員/ AI・ITエンジニア
愛称: ケーイチ
1999年2月生まれ。大学へ現役進学後数ヶ月で通信キャリアの営業代理店を経験。営業商材をもとに100名規模の学生団体を構築。個人事業主として2018年〜2020年2月まで活動したのち、2020年4月に広告営業事業を営む株式会社TOYを創業。同時期にITの可能性を感じプログラミングを始め、現在はITエンジニアとして活動中。2021年にLeograph株式会社に参画し、AI研究開発やWebアプリ開発などを手掛ける。 「Don't repeat yourself(重複作業をなくそう)」「Garbage in, Garbage out(無意味なデータは、無意味な結果をもたらす)」をモットーにエンジニア業務をこなす。
【得意領域】
業務効率化AIモデル開発
事業課題、戦略工程からシステム開発
Webマーケティング戦略からSaaS開発